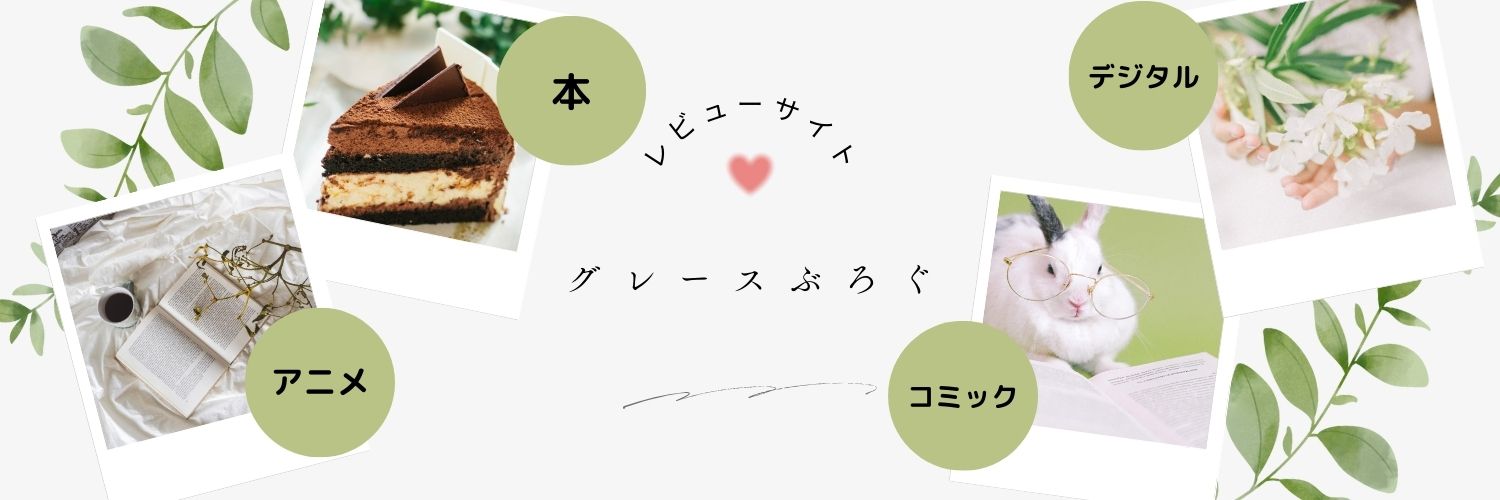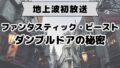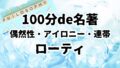(5)告白
https://www.nhk.jp/p/hikarukimie/ts/1YM111N6KW/episode/te/M9NYX64P3N/
初回放送日:2024年2月4日
道長(柄本佑)が右大臣家の子息であり、6年前に母を手にかけた道兼(玉置玲央)の弟であることを知ったまひろ(吉高由里子)はショックを受けて寝込んでしまう。事態を重く見た、いと(信川清順)はおはらいを試みる。一方、まひろが倒れたことを聞いた道長は、自らの身分を偽ったことを直接会って説明したいとまひろに文をしたためる。直秀(毎熊克哉)の導きでようやく再会することができたまひろと道長だったが…
告白
タイトルの「告白」は
三郎は藤原道長である事を
まひろが母を殺したのは道長の兄・道兼であった事を
それぞれ告白するということを意味しています。
五節の舞姫の後日談から始まります。
上級貴族の前で五節の舞をする少女たちは独身の女の子たちです。
この舞の後で上級貴族が見初めて通い婚が始まるというのは「あるある」な話だったようです。
冒頭で倫子のサロンで赤染衛門らがちょっと噂話をしています。
この話のネタ元は源氏物語の「乙女」だと思います。
源氏物語の中でも主人公の息子がこの五節の舞で踊っている少女の下に通います。
この少女が父の乳母の息子の娘です。
上級貴族が身分のそれほどでもない娘との出会いの場でもあったという事なのでしょうね。
まひろが五節の舞姫で倒れたのは三郎が道長だった事ではなくて母を殺した道兼がそこにいたからでしたが、この辺はフィクションなので(笑)
詮子さまの心が癒えない
詮子さまは上座に座るようになりました。
前回までは詮子さまは自宅でくつろいでいる感じでその屋敷の娘としてのびのびとしている風でしたが、自分の夫を毒殺しようとしていたのが父と兄だったという現実を知って気持ちも変わったのでしょうね。
父と次兄(道兼)を明らかに避けているし、長兄(道隆)に会う時も上座に座っています。
宮中で謁見するがごとく、道隆も正装で詮子さまの前に座るようになっています。
一応、「兄上」とはいうものの、詮子が信用していない事がヒシヒシと伝わってきました。
詮子にとっても自分の息子(親王であり東宮)を何があっても守るし、夫を遠ざけた原因を作った父と兄を許す気にはなれなかったんだろうと思います。
「裏の手」があるという詮子。
それは第6回で明らかになります。
倫子の父・源雅信と手を組む事でした。
弟・道長と倫子を結婚させてその娘を自分の息子(一条天皇)に入内させるという事なのでしょう。
壮大な計画が始まります。
花山天皇と女御・忯子
サイコっぷりが強調される花山天皇は理想論ばかりを押し付けて自分の叔父や好きな人に実権を握らせて旧組織の貴族たちにはすっかり嫌われています。
まともな反応をしているのが藤原実資だけですが、この実資は「小右記」を書いた人物です。
天皇をおいさめしろとか理想論だけではどうしようもないとか実直な人間です。
実資は長く官吏として活躍した人物なので彼の書いた「小右記」はとにかく長いものです。
物語ではないので面白いかと言えば、そういう事もでもありません。
当時の貴族の事を知るためにはとても有効な記録です。
ただ、権力闘争で天皇でさえ何度も変わった時代に長い期間その地位にいたという事は実直で官吏として有能で権力争いとは一線を置いていたというのが本当の所だと思います。
そんな実資でさえ、花山天皇の理想論は良くないと思っていたという設定です。
(この大河の設定という事ですよ)
花山天皇のサイコっぷりは後の世の物語「栄花物語」「大鏡」にも出てきますが、これは創作というのが大方の見方です。
藤原家の正当性を示すために花山天皇を悪者にしたという事でしょう。
ですが、花山天皇が女御・忯子を得に寵愛していたというのも本当の事です。
この女御が懐妊して後、忯子が亡くなってしまうのですが、ここを陰謀論とするのか否か…。
現実として宮中は権力争いの場で女御に正式な親王が生まれてしまえばまた権力争いの種が出来てしまいます。
花山天皇に世継ぎが生まれずに藤原家の縁故の天皇が即位してくれた方が政治がしやすいからです。
この作品を観て花山天皇について考えてみたのですが、花山天皇からしてみると「味方」は全然いなかったわけです。
忯子が入内するまでは有力な貴族からの輿入れはありませんでした。
劇中でも倫子が五節の舞姫をまひろに譲ったのも花山天皇の目に留まって自分が入内するようなことがあっては困ると思った事が嫌だと思ったからという事になっています。
実際は、中継ぎの天皇に自分の娘を入内させるという上級貴族はいなかったという事なのだと思いますけれど。
学びの場の貴公子たち
道長・公任・行成・斉信の4人が学びの場での雑談は今回も興味深いものでした。
官吏になる前の勉強会みたいなものですかね?
ここで彼らのスペックを再掲
後に主要な四納言になっていきます
道長:大納言の息子:姉は詮子(次期天皇の母)
公任:関白の息子:姉は遵子(円融天皇の中宮・子供は無し)
斉信:右大臣の息子:妹は忯子(花山天皇の女御・懐妊後死亡)
行成:歌人・藤原義孝の息子:字が上手
面白いのは天皇の外戚というのも大事な事なのですが、意外に学業も大事だという事がこのメンツを観てても分かります。
権力争いに公任は負けてしまいますが、歌や学問という部分では今に残るものも多いです。
そう思えば道長は百人一首にも選ばれていませんし、有名な歌はあまりありませんね。
面白いのは道長の日記がうっかり現代に残ってしまったというくらいです。
(この日記も世界的には価値があるモノですけれどね。詳細はこちら)
蜻蛉日記の作者が出てきた
蜻蛉日記で有名な「道綱の母」が出てきました。
この人、実は兼家の妾なんです。
こんな有名な人が出て来るのもこの時代の面白さですね。
「蜻蛉日記」は夫に大事にされなった女性のボヤキのような日記なのですが、「道綱の母」は意外に商魂たくましかった人のようで自分の不幸を売りに出してベストセラー作家になったというようなイメージが本当の所だったようです。
道綱の母はこの時代の美人中の美人だったのですが、私たちが思っている美人とはちょっと違います。
・和歌もうまい
・裁縫も得意
・染物も上手
これが全部そろったのが道綱の母で彼女自身もそれを自慢げに思っていたのがありありと浮かびます。
「道綱の母」にしてみれば「私って高級な女なの!なのに妾ってあり得ないじゃん!」みたいな感じなのですよね。
だから、蜻蛉日記を読んでいても鼻につくような感じがするのはその辺のような気がします。
道長の異母兄の道綱自身は出世は遅れたようですが、道長自身とは特に権力争いになる事もなく、終わったようです。
「毒にも薬にもならない」というのが本当の所だったと思います。
呪詛が本気であった時代
安倍晴明が出てきましたね。
この大河の描かれ方の安倍晴明が一番本当のイメージに近いのではと思います。
映画やドラマ、漫画でも描かれた「陰陽師」も好きなのですが、当時の陰陽道は政治と直結していましたから。
陰陽道で良い日を選んで悪い日は避ける。
今でも「縁起を担ぐ」ということが多々ありますが、これを丸ごと政治に盛り込んだわけです。
陰陽師が何でも日程を決められる立場にあったという事です。
意外に陰陽師が裏の実権を持っていたと言っても過言ではないように思います。
安倍晴明は実在の人物です。
今昔物語の中にも出てきますが、映画などにあった式神や魑魅魍魎(ちみもうりょう)を連れて行くという記述はほんの一部です。
後は「小右記」「御堂関白日記」にも出て来る式次第をつかさどる一人であったことが分かります。
(陰陽師という言われ方は当時からのものです)
大河ドラマの中では兼家が晴明に女御(花山天皇の后)の懐妊を呪詛するように命じます。
これは兼家であっても許される事ではありません。
ただし、御簾の後ろに公卿たちが並んでいる事で全員の総意である演出が施されています。
帝よりも公卿たちが実権を握っているという事が暗に示されたシーンです。
紀行:雅楽・市比賣神社
平安時代 宮廷貴族たちが集い楽しんだ音楽「雅楽」
大河ドラマ「光る君へ」~第5回「告白」より
5世紀から9世紀にかけ大陸からもたらされた楽器演奏と舞に日本古来の歌や舞が融合して平安時代に完成したといいます。
器楽の合奏 管弦は世界最古のオーケストラといわれています。
吹物(ふきもの)と呼ばれる管楽器。
打物(うちもの)の打楽器
弾物(ひきもの)の弦楽器で編成されています。
貴族たちの優雅な遊びとして合奏する様子が「源氏物語」にも描かれています。
平安時代創建の市比賣神社(いちひめじんじゃ)
京都の神社や寺などで継承されてきた雅楽を伝え広めようと地元の人達に雅楽指導を行っています。
平安時代から変わらないみやびな調べは今も京都で継承されています。
宮内庁で行われる雅楽がありました。
とても厳かな感じがしますね。
雅楽は神社なんかで聞く楽器だとイメージすればよく分かると思います。
市比賣神社は京都の河原町の商店街の中にあります。
雅楽とも縁が深いとは思いませんでした。
次に訪れるときはこの辺もじっくり味わいたいと思います。

今回も面白かったです。
次回はいよいよ清少納言登場。
楽しみです。
光る君へ~第4回~五節の舞姫⇐前の回
次の回⇒光る君へ~第6回~二人の才女
放送リスト
第1回「約束の月」 – 2024年1月7日
第2回「めぐりあい」 – 2024年1月14日
第3回「謎の男」 – 2024年1月21日
第4回「五節の舞姫」 – 2024年1月28日
第5回「告白」 – 2024年2月4日
第6回「二人の才女」 – 2024年2月11日
第7回「おかしきことこそ」 – 2024年2月18日
第8回「招かれざる者」 – 2024年2月25日
第9回「遠くの国」 – 2024年3月3日
第10回「月夜の陰謀」 – 2024年3月10日
第11回「まどう心」 – 2024年3月17日
第12回「思いの果て」 – 2024年3月24日
第13回「進むべき道」 – 2024年3月31日
第14回「星落ちてなお」 – 2024年4月7日
第15回「おごれる者たち」 – 2024年4月14日
第16回「華の影」 – 2024年4月21日
第17回「うつろい」 – 2024年4月28日
第18回「岐路」 – 2024年5月5日
第19回「放たれた矢」 – 2024年5月12日
第20回「望みの先に」 – 2024年5月19日
第21回「旅立ち」 – 2024年5月26日
第22回「越前の出会い」 – 2024年6月2日
第23回「雪の舞うころ」 – 2024年6月9日
第24回「忘れえぬ人」 – 2024年6月16日
第25回「決意」 – 2024年6月23日
第26回「いけにえの姫」 – 2024年6月30日
第27回「宿縁の命」 – 2024年7月14日
第28回「一帝二后」 – 2024年7月21日
第29回「母として」 – 2024年7月28日
第30回「つながる言の葉」 – 2024年8月4日
第31回「月の下で」- 2024年8月18日
第32回「誰がために書く」- 2024年8月25日
第33回「式部誕生」- 2024年9月1日
第34回「目覚め」-2024年9月8日
第35回「中宮の涙」-2024年9月15日
第36回「待ち望まれた日」-2024年9月22日
第37回「波紋」-2024年9月29日
第38回「まぶしき闇」-2024年10月6日
第39回「とだえぬ絆」-2024年10月13日
第40回「君を置きて」-2024年10月20日
第41回「揺らぎ」-2024年10月27日
第42回「川辺の誓い」-2024年11月3日
第43回「輝きののちに」-2024年11月10日
第44回「望月の夜」-2024年11月17日
第45回「はばたき」-2024年11月24日
第46回「刀伊の入寇」(といのにゅうこう)-2024年12月1日
第47回「哀しくとも」-2024年12月8日
第48回(最終回)「物語の先に」-2024年12月15日
登場人物が書いた本
源氏物語
ネット配信はこちら
キャスト一覧
主要キャスト一覧
まひろ/紫式部 (むらさきしきぶ) 吉高 由里子
藤原 道長 (ふじわらのみちなが) 柄本 佑
藤原 為時 (ふじわらのためとき) 岸谷 五朗
ちやは 国仲 涼子
藤原 惟規 (ふじわらののぶのり) 高杉 真宙
藤原 兼家 (ふじわらのかねいえ) 段田 安則
時姫 (ときひめ) 三石 琴乃
藤原 道隆 (ふじわらのみちたか) 井浦 新
藤原 道兼 (ふじわらのみちかね) 玉置 玲央
藤原 詮子 (ふじわらのあきこ) 吉田 羊
高階 貴子 (たかしなのたかこ) 板谷 由夏
ききょう/清少納言 (せいしょうなごん) ファーストサマーウイカ
安倍 晴明 (あべのはるあきら) ユースケ・サンタマリア
源 倫子 (みなもとのともこ) 黒木 華
源 明子 (みなもとのあきこ) 瀧内 公美
藤原 実資 (ふじわらのさねすけ) 秋山 竜次
藤原 公任 (ふじわらのきんとう) 町田 啓太
藤原 斉信 (ふじわらのただのぶ) 金田 哲
藤原 行成 (ふじわらのゆきなり) 渡辺 大知
源 俊賢 (みなもとのとしかた) 本田 大輔
源 雅信 (みなもとのまさのぶ) 益岡 徹
藤原 穆子 (ふじわらのむつこ) 石野 真子
藤原 頼忠 (ふじわらのよりただ) 橋爪 淳
藤原 宣孝 (ふじわらののぶたか) 佐々木 蔵之介
藤原 定子 (ふじわらのさだこ) 高畑 充希
藤原 彰子 (ふじわらのあきこ) 見上 愛
藤原 伊周 (ふじわらのこれちか) 三浦 翔平
円融天皇 (えんゆうてんのう) 坂東 巳之助
花山天皇 (かざんてんのう) 本郷 奏多
一条天皇 (いちじょうてんのう) 塩野 瑛久
直秀 (なおひで) 毎熊 克哉
赤染衛門 (あかぞめえもん) 凰稀 かなめ
乙丸 (おとまる) 矢部 太郎
百舌彦 (もずひこ) 本多 力
いと 信川 清順
藤原 道綱 (ふじわらのみちつな) 上地 雄輔
藤原 寧子 (ふじわらのやすこ) 財前 直見
藤原 隆家 (ふじわらのたかいえ) 竜星 涼
さわ 野村 麻純
絵師 (えし) 三遊亭 小遊三
藤原 忯子 (ふじわらのよしこ) 井上 咲楽
藤原 義懐 (ふじわらのよしちか) 高橋 光臣
三条天皇 (さんじょうてんのう) 木村 達成
藤原 顕光 (ふじわらのあきみつ) 宮川 一朗太
朱 仁聡 (ヂュレンツォン) 浩歌
周明 (ヂョウミン) 松下 洸平
藤原賢子(ふじわらのかたこ)南 沙良
あかね / 和泉式部(いずみしきぶ)泉 里香
敦康親王(あつやすしんのう)片岡千之助
双寿丸(そうじゅまる)伊藤健太郎
スタッフ一覧
脚本 : 大石静
語り : 伊東敏恵
副音声解説 : 宗方脩
タイトルバック映像 : 市耒健太郎
題字・書道指導 : 根本知
制作統括 : 内田ゆき、松園武大
プロデューサー : 大越大士、高橋優香子
広報プロデューサー : 川口俊介
演出 : 中島由貴、佐々木善春、中泉慧、黛りんたろう、原英輔、佐原裕貴 ほか
時代考証 : 倉本一宏
風俗考証 : 佐多芳彦
建築考証 : 三浦正幸
芸能考証 : 友吉鶴心
平安料理考証 : 井関脩智
所作指導 : 花柳寿楽
衣装デザイン・絵画指導 : 諫山恵実