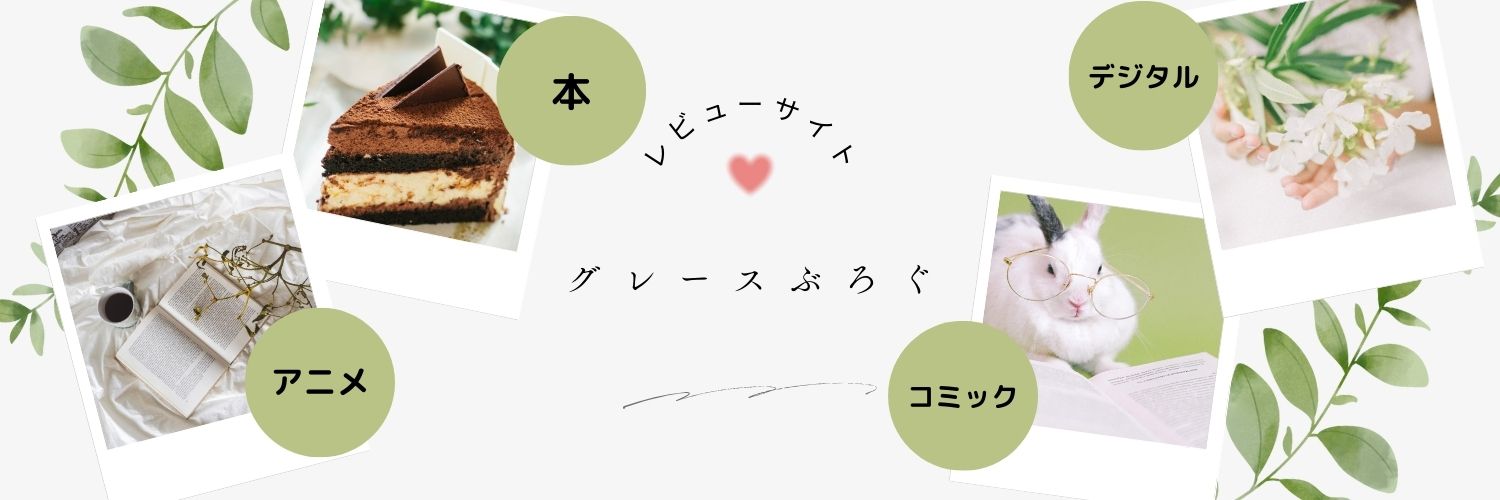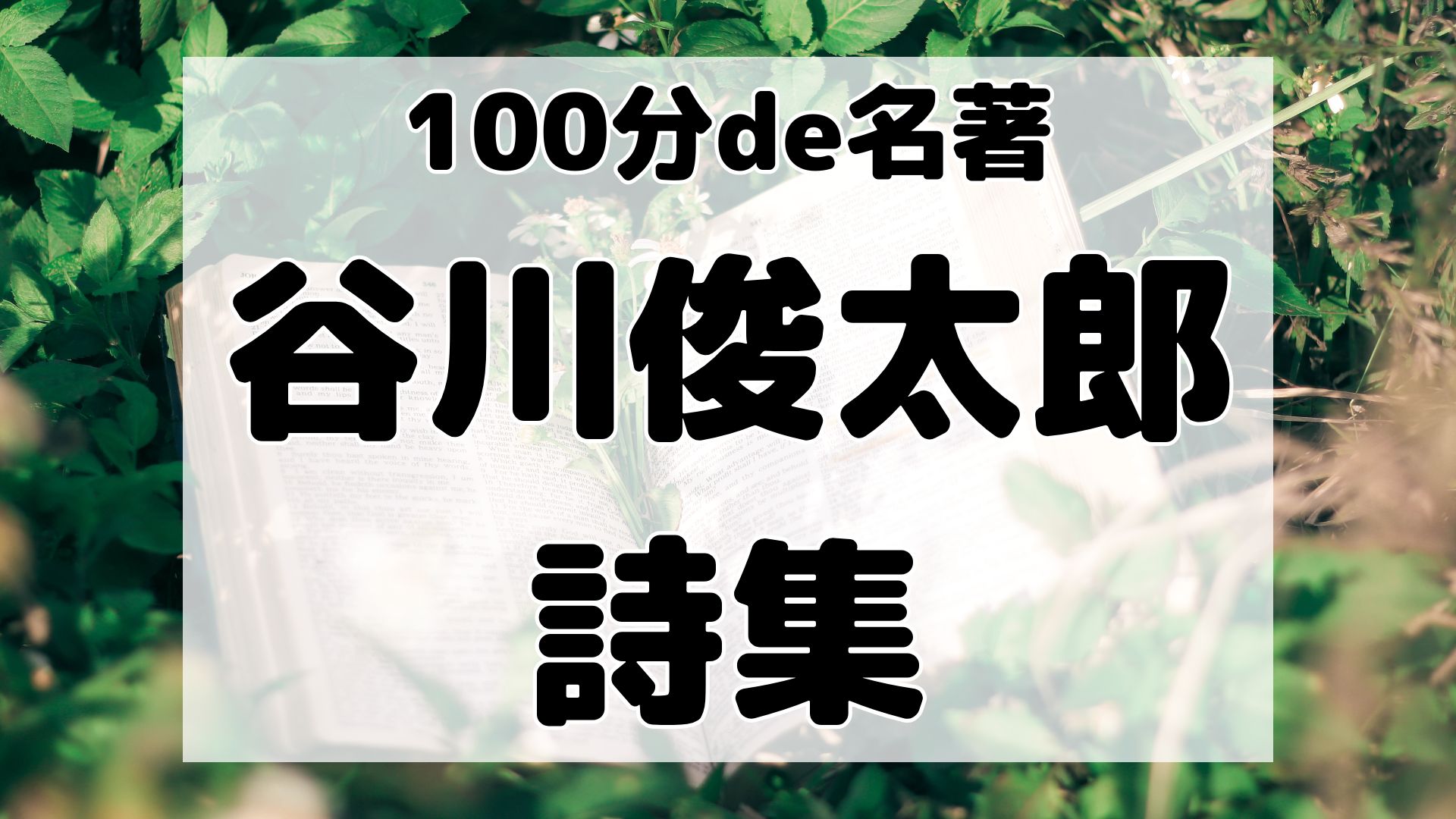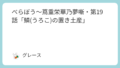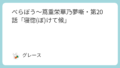2024年。天国に旅立たれた谷川俊太郎さん。
多くの人の『心』に影響を与えた方でないかと思います。
今回は私自身の思いやそれに対する本の思い出を語っていきます。
各回、目次からジャンプできます。
第1回 詩人の誕生
【初回放送】2025年5月5日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
弱冠18歳にして詩人・三好達治に見いだされ、21歳にはデビュー詩集「二十億光年の孤独」を発表した谷川俊太郎。「学校が楽しかった記憶はない」と述懐する谷川は、たびたび教師に反抗し大学進学も拒否する。理解者がいない、絶対的ともいえる孤独の中で、彼はひたすらノートに詩を書き続けた。そこで深く味わった「かなしみ」は、デビュー作につながり、彼の生涯を通奏低音のように彩っていく。第一回は、「二十億光年の孤独」「かなしみは」など初期の作品を通して一人の詩人が誕生するまでを見つめ、彼の詩の原点ともみえる「かなしみ」という言葉の深い意味に迫っていく。
谷川俊太郎さんは誰もがどこかで出会っている
谷川俊太郎さんと聞いて、知らない日本人は少ないと思います。
お名前までは覚えていなくても、子どもの頃に教科書に載っていたあの「詩」や「お話」、「翻訳」などで、どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。
テレビで出会った「俊ちゃん」
私は、ほとんど本でしか谷川さんを知りませんでしたが、阿川佐和子さんが司会をされていた番組にゲストとして出演されたことがあります。
今にして思えば、とても貴重な番組でした。
阿川佐和子さん自身も、お父様が作家でいらっしゃるので、幼いころから文壇の文豪や文人たちと非常に親しい間柄でいらっしゃったようです。
そのなかで、阿川佐和子さんは谷川俊太郎さんを「俊ちゃん」と呼ぶほど親しく、文豪・谷川俊太郎ではなく、「俊ちゃん」という一面を垣間見ることができました。
(番組放送は2014年5月。谷川俊太郎さんはすでに82歳でいらっしゃいました)
生きている文豪に驚く私
「俊ちゃん」は、阿川佐和子さんの番組放送時点ですでに誰もが知る文豪です。
そのため、「亡くなった人」と思われることもしばしばあり、それがけっこう傷つく、と語っておられました。
実はこの話、私も「そう思っていた」一人でした。
私自身、幼少の頃からその名を聞いていた文豪が、まさかご存命とは思っておらず、阿川佐和子さんに「俊ちゃん」と呼ばれていることに、少なからず衝撃を受けたのです。
長く第一線で活躍し続けた人
成功されたのが早かったため、活躍の期間も長かったのだと思います。
そのために、教科書に載るような方がご存命だとは、私も非常に驚きました。
ですがこの後、2024年に天国へと住まいを移されるまでの10年間、その文筆活動が止まることはありませんでした。
書店でよく売れている絵本を見かけたことがあるのですが、その原作も谷川俊太郎さんによるものでした。
絵本『へいわとせんそう』との出会い
タイトルは『へいわとせんそう』。
この絵本は、ページの見開きで「平和」と「戦争」を対比しています。
「イラストと谷川さんのショートコメント」で構成されており、イラストはモノクロ一色のみですが、見たことがあるという方もいらっしゃると思います。
タイトルは「へいわとせんそう」です。「せんそうとへいわ」ではないところがミソです
シンプルな絵と言葉が語るもの
そのタイトル通り、平和な時と戦争の時の絵が対比されています。
最も印象的な対比は「ぎょうれつ」です。
平和な時の行列は一般の人々の行列ですが、戦争の時の行列は兵隊さんの行列です。
私のつたない文章だけでは伝わらないと思いますが、ぜひ本を手に取ってお読みいただきたいです。
お子さんへのプレゼントにも良いですし、やはり大人が読んでも心に染みる本だと思います。
第2回 「生活」と「人生」のはざまで
【初回放送】2025年5月12日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
1960~70年代、子どもも生まれ、家計を支えるために数多くの詩を創らなければならない苦しい時代を過ごした谷川俊太郎。「書けないのなら/書けないと書かねばならない」等と苦しさがことばの端々からにじみ出てくる一方で、「一番安定して幸せな時期」と語っている通り、ことばの力によってその苦しさを昇華し、自分の糧にしていった彼の模索も見えてくる。第二回は、「ここ」「ほほえみ」「ぼくは言う」「木」といった詩を読み解くことで、ただ「生活」にのみ埋もれるのではなく、そこから糧を見出し、新たな表現を掬い上げていこうとする谷川俊太郎の試みを追う。
翻訳作品としての「スイミー」
今回は、たくさんの翻訳をされていたことも紹介されました。
番組内では「スイミー」が紹介されました。
「スイミー」も、とても有名ですね。
教科書に載っていた、あの「スイミー」です。
当時、暗記するほど読みました。
「レオ・レオニ」という名前のインパクト
作者の名前も面白かったですね。
原作者は「レオ・レオニ」。
その名前も、「レオ」が名前なのか? 果たして本名なのか?――当時は子どもたちの間で話題になりましたね。
楽しい思い出です。
「レオ・レオニ(Leo Lionni)」の本名は、
「レオナルド・リオンニ(Leonardo Lionni)」というそうです。
詩人・谷川俊太郎との出会い
「スイミー」を読んだ当時は、この翻訳者の「たにかわしゅんたろう」と、詩人の「谷川俊太郎」が同一人物とは、なかなか思えませんでした。
同一人物だと知ったのは、同じく彼が翻訳した「スヌーピー」シリーズを読んだときでした。
英語の勉強に使おうと思った「スヌーピー」
英語の勉強をする時に、対訳として使えるのではと思って購入したのが「スヌーピー」シリーズです。
スヌーピーなら馴染みもあるし、分かりやすいんじゃないかと思って手に取ったのが始まりです。
ですが、このシリーズの「翻訳」は対訳とは程遠く、ほとんどが意訳だったのです。
意訳の巧みさと学習の難しさ
これで純粋に英語の勉強をしようと思っていた私は、とんでもないハードルにつまずくことになります。
翻訳者の力量で意訳はとても分かりやすいのですが、英語の勉強としては程遠いものとなってしまったからです。
スヌーピーを通じて知ったアメリカ文化
実はこのスヌーピーシリーズには、解説が非常に丁寧に書かれていたことを思い出します。
「この一言」には、こんなアメリカの事情がある――ということが書かれていました。
ルーシーの人生相談に見るアメリカの精神医療
私が今もよく覚えているのが、登場人物の一人・ルーシーが、やたらと「人生相談」を受ける側になるということです。
これは、アメリカの精神医療が非常に発達していることや、何かあったら精神科で相談するという文化を示唆していました。
それこそ、「精神科医のための精神科医」がいるということも、このシリーズの解説で知ったほどです。
精神的な病気への考え方が、日本とはずいぶん違っていて、先進的だなと思ったのを思い出します。
スヌーピーの本当のタイトルは「ピーナッツ」
スヌーピーシリーズは、正確には「ピーナッツ」と言います。
これも、谷川俊太郎訳で初めて知ったことでしたね。
ギフトにもなるスヌーピーの一冊
私自身も、「スヌーピー」シリーズの中から、ちょっとギフトになりそうな本を今も大事にしています。
『スヌーピーの 大好きって 手をつないで歩くこと』です。
これについてのブログも書いていますので、どうぞお読みください。
第3回 ひらがなの響き、ことばの不思議
【初回放送】2025年5月19日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
1980~90年代、詩作だけでなく、海外の詩の翻訳などを通して、ことばそのものの響きや音楽性を再発見した谷川俊太郎は、「ひらがな」だけで詩を書くという試みを続ける。その一方で、さまざまな手法によって、人間と自然の一体感をどのように表現していくかを、ことばへの深い洞察を通じて試みていく。谷川俊太郎の詩は、ことばそのものへの深い思索、洞察によって、進化し続けていくのだ。第三回は、「なくぞ」「にじ」「さようなら」「おに」「がいこつ」といった詩を通して、彼が追究してやまなかった「ことば」への洞察を明らかにしていく。
ひらがなで書くことの意味
谷川俊太郎さんの詩は「ひらがな」が多い印象を持つ人も多いでしょう。
これも、ひらがなで書くことで、いろんな人に読みやすくし、理解できるようにするためです。
読む人によって変わる解釈
ただし、どう受け取るかはその人次第。
誰が読むか、どんな立場にあるかで、どんな印象を持つかは分かりません。
自由な解釈と書き手の覚悟
いろんな解釈で「広がる」一方で、「どう受け取られても良い」という覚悟が谷川俊太郎さんにあったのでは、と解説するのは指南役の若松英輔先生。
考えてみれば、確かにそうですね。
今で言うと、自分の解釈のはずなのに、相手を批判して炎上するようなこともあります。
SNSで炎上するような時代ではなかったかもしれませんが、批判や勝手な解釈で、書き手である谷川俊太郎さんに怒りが向けられるということが、当時もあったのだろうと推察されます。
きっと、手紙や何かで「苦情殺到」なんていうことも、覚悟の一つだったのかもしれません。
子どもにも届くことば
ひらがなで書くことで、大人だけでなく子どもも読むことができます。
また、子どもが自分で読むことで、自分なりの考えで解釈していくわけですが、これを「子どもを信頼している」とも受け取れるというのです。
子どもだから「分からないだろう」というのではなく、「敬意」があるというのです。
これも今で言えば、「子どもをリスペクトしている」といったところでしょうか。
難しさよりも、やさしさを
「簡単そうに作ることが一番大変」というのは伊集院さんの言葉でしたが、若松先生も「難しくすることが高尚と思われる現代で、その全く逆を行っている」と言います。
私もまた、この言葉に救われました。
難しい言葉や高尚な表現でなくてもいいのです。
簡単な言葉でも相手に伝わり、意思の疎通がなければ意味がないのですね。
紹介された詩の一部
「わるくち」
悪口を言うと、言い返されたり、嫌な言葉で返されたりするということを表現しています。
これは、大人の世界でも同じですね。
「マザーグース」
イギリスで昔から伝わる童謡のようなものですね。
有名なところでは「ロンドン橋」でしょうか。
これを「詩」として紹介したのが谷川俊太郎さんで、しかも「ひらがな」で書かれているのです。
発表された当時、一気に流行ったそうです。
「なくぞ」
これも主語がなく、「なくぞ」ということで、子どもかもしれないし、神様かもしれません。
自然かもしれません。
「泣く」のではなく「鳴く」かもしれません。
受け取る人によって、これだけ解釈が変わるのです。
「さようなら」
「ぼくはもう行かなければならない」という冒頭の言葉から、若松先生は子ども自身の死を連想させると言います。
これも、またどこかに行くということであり、立場による解釈をここでも痛感します。
谷川俊太郎さんの詩を読んでみませんか?
他にもたくさん紹介されました。
皆さんも一度、谷川俊太郎さんの詩集を読んでみませんか?
第4回 こころとからだにひそむ宇宙
第4回 こころとからだにひそむ宇宙
【放送時間】2025年5月26日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
「いまからぼくは遺言する」「闇がなければ光はなかった/闇は光の母」……人生後半に至り、谷川俊太郎の詩には「死」にまつわる言葉や「闇」「夜」といった暗い言葉が、たびたび出てくるようになる。だが、詩の雰囲気はむしろ静謐で、明るさすら感じられる。そこには「生の根源」「存在の根源」にまっすぐ迫ろうとする彼の志向性がみてとれる。第四回は、「言葉は」「臨死船」「闇は光の母」「生まれたよ、ぼく」といった詩を通して、「生きていること」の根源に迫ろうとする谷川俊太郎の境地に迫るとともに、「詩の力」が私たちに何をもたらしてくれるのかを深く考えていく。
最終回は谷川俊太郎の最晩年に迫る
最終回となった第4回は、谷川俊太郎の最晩年の活動に迫ります。
朗読会や、各地に自ら赴いての新しい試みがありました。
一観客としての貴重な体験
私も一人の観客として、この活動を拝見したことがあります。
そう思えば、非常に幸運な巡り合わせだったのかもしれません。
好々爺という存在
「とても優しそうな好々爺」というのは、こういう方なんだと思いました。
また、この素敵なお爺様は、頭脳明晰で、実に聡明なお人柄でもありました。
これは本当に素晴らしかったです。
即興の詩に驚き
なんと、その場の雰囲気に合わせて即興で詩を作るということもされていて、非常に驚きました。
「えっ?これアドリブ?この場で作っちゃった???」と、その場に居合わせた多くの人が思ったことでしょう。
これを全部覚えていて、文字起こしができたらよかったのですが、一言一句は覚えておらず、申し訳ないです。
「言葉の変遷」というテーマ
ただ、少し覚えているのは「言葉の変遷」に関する詩で、ラジオからテレビ、そしてネットへと活動の場が移り変わる様子を表現していたと思います。
これは、ちょっとしたことで「炎上」してしまうことや、またそれすらもすぐに消え去り、次の炎上へと移っていく様子を描いていました。
「ああ、なるほどなあ」とその時は思ったのですが、正確には覚えておらず、無念です。
(皆さんにご紹介できずに、申し訳ありません!)
今は「炎上」と言われますが、その前も「苦情」や「クレーム」、「つるし上げ」といった言葉が存在していたのですね。
「言葉」は武器にもなり、平和のためにもなり、その使い方を死ぬまで追求した方だったと、私は思います。
宗教に寄らない普遍的な詩の世界
番組の中でも、死後の世界や宇宙をモチーフにした詩がたくさん紹介されましたが、それが宗教的というよりも、誰しも思い当たるような身近なものでした。
活躍年数が長く、それこそ死の直前まで活動されていたそのお姿を、多くの人が「記憶」しているのですね。
これからも、これら多くの詩を読んでいきたいと思います。

今回は、谷川俊太郎先生の思い出話や私自身が影響を受けた事を中心に書いていく事になりました。
読んでいただいてありがとうございます。
皆さんの心のエネルギーになれば良いなあと思います。