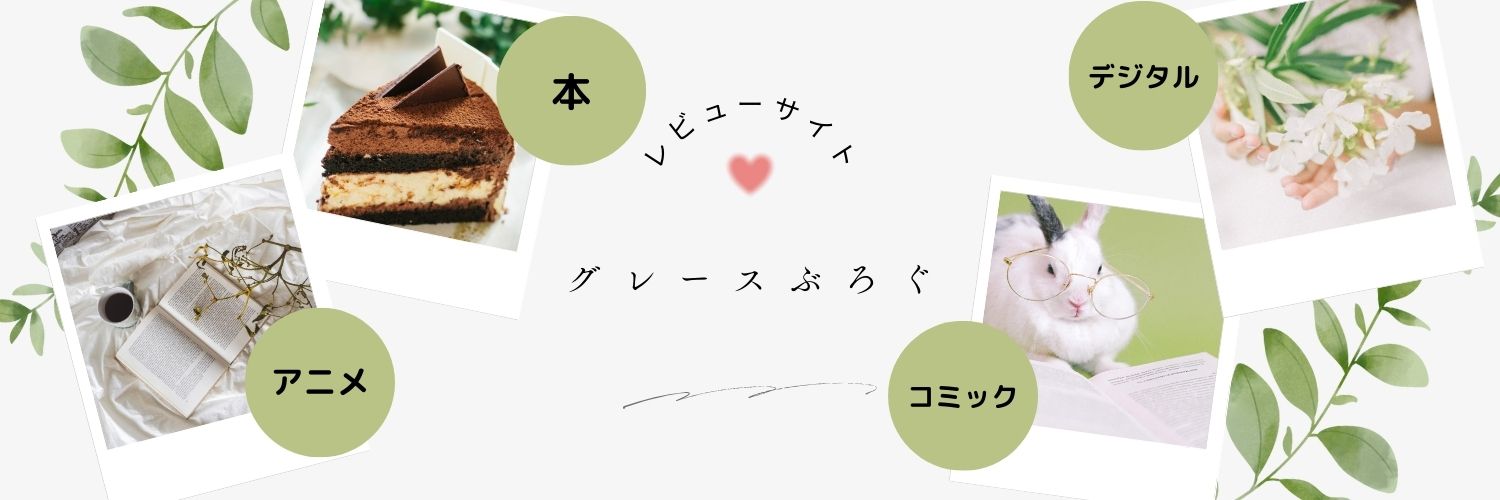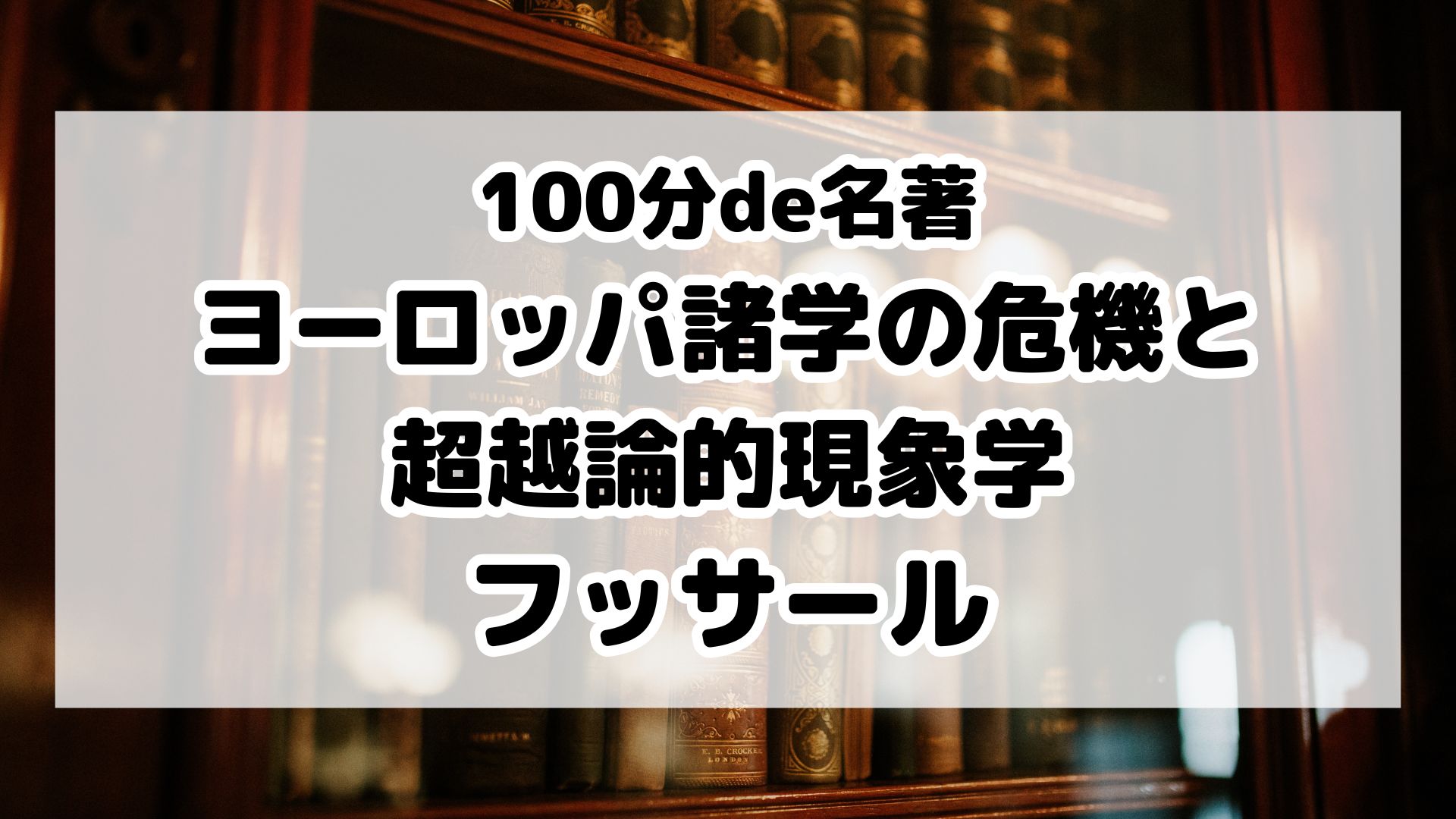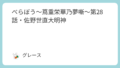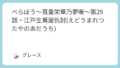難解な哲学書。
100分de名著史上最長のタイトル。
私を含め、名前しか聞いた事もないという人も多いと思います。
指南役の西研先生も終始、入門的な説明に徹してくれました。
まさか、あの難解で有名な哲学書が「面白い」と思える日が来るなんて!
私も今回は感想に徹して書いて行こうと思います。
第1回・学問の「危機」とは何か
初回放送日:2025年7月7日
20世紀前半、近代科学は著しく発展したが「価値や生きる意味」について語らず価値を語る哲学者たちはそれぞれ勝手な説を唱えるのみであった。フッサールは「科学の有効性と人間的な価値とを、ともに説得力をもって解明する」という根源的な課題のために、「どう考えたら誰もが納得できる場所を確保できるのか」を考え抜く。そして、「意識に現れるもの」に立ち戻り、そこからすべての学問の基盤を築き直す「現象学」構想する。
フッサールはこんな人
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生誕/死没 | 1859年4月8日〜1938年4月27日 |
| 出身/背景 | モラヴィア(当時オーストリア帝国)、数学→哲学へ転向 |
| 主要概念 | 現象学、ノエシス・ノエマ、エポケー、現象学的還元、志向性、時間意識構造 |
| 後世への影響 | 現代哲学、認知科学、文化思想への多大な波及 |
現象学の祖
ユダヤ人の哲学者で、ナチス・ドイツによって行動を制限されていたフッサール。
この「現象学」という言葉は、フッサールによって確立されたと言われています。
この作品は三部から成りますが、第一部と第二部は国外から、最終巻となる第三部は彼の死後、弟子たちによって編纂されました。
ユダヤ人として迫害されるもドイツで天寿を全うする
ユダヤ人の哲学者といえば、ハンナ・アーレントなども注目されます。
アーレントは国外で過ごしましたが、フッサールはドイツで命を全うしました。
ナチス・ドイツの台頭は1933年で、フッサールは1938年に亡くなっています。
ギリギリ、収容所に送られるような時代までは生きていなかったのではないかと思います。
ただ、天寿を全うするまでの5年間は、大学での居場所も、自らの発表の場も制限されていたのです。
その、たった5年の間にこの本が書かれたということになります。

すでに国際的に有名な哲学者であったフッサールでしたが、ドイツ国内ではかなり活動を制限されていたということになります。
ですが、この期間には執筆に徹したため、草稿の量は膨大になったのです。
第2回・科学の手前にある豊かな世界
(2)科学の手前にある豊かな世界
初回放送日:2025年7月14日
近代科学が、世界をそのまま写し取っていると信じる「客観主義」に陥ってしまったのはなぜか。幾何学と物理学は自らの基盤としている「物事を見たり触ったりしている具体的な知覚の世界」という共通基盤を忘れてしまったからだという。フッサールはこれを「生活世界」と呼び、そこから幾何学と物理学が発生してきたという。私たちが「価値の問題」や「感情の問題」を考えるためには、生活世界に立ち戻らなければならないと訴える。
科学と実証主義がもたらした影
科学による実証主義が、戦争を――世界大戦という人類の多大なる犠牲へと――繋げたのではないかというのは、残念ながら真実であろうかと思います。
世界大戦ということになって戦線は世界中に拡大し、その犠牲者も一気に増えました。
また、科学があり、豊かであるからこそ引き際もどんどん後ろにずれ込み、ボロボロになるまで人類は戦争をやめられなかったのです。

戦火の拡大が科学の躍進と関係しているというのは皮肉な話です。
フッサールの二つの世界:生活世界と客観的世界
これをフッサールは、二つの世界――「日常の世界=生活世界」と「物理的な世界=客観的な真の世界」――に分けて考えます。
聞いただけで難しい話ですね。私も同じです。
そこで、指南役の西研先生のお話を聞きながら、さらに私なりに「こうであろう」ということを考えていきたいと思います。
「生活世界」は普段の生活に根ざした世界です。
たとえば、火は温かい、火に紙を近づけると燃える――といったような、私たちが日々の暮らしから得る知識です。
一方、「客観的な真の世界」というのは、物理的・数学的なデータに基づく知識を指します。
この二つの違いは、「生活世界」は感覚的なもの、
「客観的な真の世界」は学術的・理論的に捉えたもの――ということになります。
そう分けて考えればいいのかな、と思いました。
主観と客観のはざまで
一つのものでも、別の方向から見ることで、より広い世界を捉えることができるのです。

ただし、この二方向の「客観的」と「主観的」な立場が、まったく相反する場合もあります。
そして、その二つの相反するものですら、結局は人間の脳の中の答えでしかない――という、なかなか堂々巡りのような話にもなりました。
でも、面白いです。
第3回・現象学的還元によって見えるもの
(3)現象学的還元によって見えるもの
初回放送日:2025年7月21日
科学や知覚の源泉として見いだされた「生活世界」。だが、そこにとどまるのでは不十分だとして、フッサールは「現象学」という方法を研ぎ澄ます。客観的な世界が確かに実在するという常識すら、いったん括弧にいれることで、意識体験の場だけにフォーカスし、世界が実在するという信念がどう形成されてくのかを解明する。それにより科学至上主義も退けることができるし、客観主義か相対主義という対立も乗り越えられる。
「客観」とは何かを問い直す思考実験
客観的な事実をいったん置いての思考実験。
これらは、「客観的」と思うこと自体が人の主観であるという、なんとも壮大な話になってきました。
これが、いわゆる主客一致の難問と言われるものです。
主客一致の難問=主観が客観にどうやって一致し果たして正しい認識を得られるのか?
生活世界とフッサールの現象学
最近「生活世界」という言葉に触れる機会があり、あらためてフッサールの現象学に思いを巡らせました。
科学や知覚の出発点としての「生活世界」。私たちが普段当たり前に感じているこの世界は、実は単なる背景ではなく、深い意味を持っているんですね。
でも、フッサールはそこにとどまらなかった。
むしろ「生活世界」を足がかりにしながら、それを一歩引いた視点で捉え直そうとしたのです。
たとえば、「この世界は客観的に実在している」という、私たちがつい信じてしまう常識すら、一旦カッコに入れて脇に置く(彼の言葉で言う「判断停止」)。
そうすることで、意識の中でどのように「世界がある」と感じられているのか、そのプロセスそのものに光を当てようとしました。
このアプローチ、すごく静かで地味に見えるけれど、実はとてもラディカル。
科学だけが真実を語るわけではないし、かといって全部が相対的だというわけでもない。
フッサールはその両極を超えようとしたんだな、と感じました。
「現象学」は難しいとよく言われるけれど、こうして見ていくと、私たちの当たり前を少し揺さぶってくれる、とても人間的な営みなのかもしれません。
善悪を超えて考えるために
伊集院さんの例えがものすごくよく分かりました。
宗教の上で「これが正しい」として「それ以外は悪い」としてしまった場合、人は戦争や過ちを繰り返してしまった事実もあります。

この上で、「善悪」という二つの側面でなく、もう一つの客観性があれば、違う結果に導けるのではと思いました。
勧善懲悪では、何も解決しないのかもしれません。
前回の侍女の物語に続いて、今の時代に照らして、あらためて考え直す必要がありそうです。
第4回・現象学で何ができるか
(4)現象学で何ができるか
初回放送日:2025年7月28日
私たちは通常「正義」「幸福」といった言葉について、人によってその意味は相容れないことも多いから、突っ込んで議論しても無駄だと考えがちだ。ところが、「現象学」の「本質観取」という方法を使えば、議論の共通の基盤が見えてくる。「どういうときに、どういう形で、人は正義や幸福を感じとるのか」については、対話していくと自ずと収れんする「意識への現れ方」に注目すると、共通基盤の中で深い議論ができるというのだ。
「正義」や「幸福」は、人それぞれ…だけじゃなかった!
「正義」とか「幸福」って、人によってまったく受け取り方が違う。
だから、こういう話題を深く議論しても結局は平行線…そんなふうに感じたこと、ありませんか?
私もずっとそう思っていました。どうせ答えなんて出ないし、無理に話しても価値観の押しつけ合いになりがちだなって。
でも最近、「現象学」という哲学の中にある「本質観取(ほんしつかんしゅ)」という考え方を知って、ちょっと目からウロコでした。
この方法では、「正義って何? 幸福って何?」といった抽象的な問いを、ただ定義のぶつけ合いで終わらせないんです。
むしろ、「人はどんなときに正義を感じるのか」「どんな形で幸福だと感じているのか」
つまり、みんなの意識の中に現れる共通の感じ方を探っていく。すると、意外にも共通点が見えてきて、深い対話ができるようになるというんです。
これはすごく希望のある視点だなと思いました。
「違い」ばかりを見ていたら対立しかないけど、「現れ方」に目を向ければ、そこにはちゃんとつながれる場所があるんだなと。

価値観がバラバラに見える時代だからこそ、こういうアプローチがますます大事になってくる気がします。
西先生による「哲学対話」の実演も!
説明だけでは分かりにくいですよね。
なるほどと思っても、個人個人が幸せと思うことは、時に一緒であったり、違ったりします。
ここで、聴講している二人による「幸福体験」が紹介されました。
「幸福とは何か?」
奥さんとおいしいご飯を食べるとき
暖かい布団
いい仕事をした後のお風呂
子供が生まれた時、指を握った瞬間
番組の後の本音の感想

意外に、ちょっとしたことで幸福を感じるものなのですね。
他者が喜んでくれること、充実感があること、ありがたいと思う気持ちが挙げられました。
【幸福とは】不安なく満たされていて、その境遇に感謝し、ありがたいと思えること。
フッサールの第三部が発行された経緯も!
ナチスに発表の場を奪われたフッサールは、第三部を発行することなく天寿を全うします。
彼の遺稿を守るため、ベルギーの学生ヴァン・ブレダがフッサールの家を訪れました。
その原稿の量は4万枚を超えたと言われています。
フッサール自身は独自の速記法を身につけており、思考と同じスピードで原稿を書くことができたそうです。
この大量の原稿をトランク3つに詰めて、スイス国境の修道女宿舎へ運び込んだのです。
当時、スイスは中立国だったため可能な判断だったとはいえ、命がけの行動だったと思います。

少し調べてみると、この原稿を守ったヴァン・ブレダという人物は、ベルギーの神父だったそうです。
彼自身の職位がナチスの検閲を逃れる要因の一つだったのではないかと思います。
フッサールの全集は40巻にも及ぶとか。
この時の原稿があったからこそ、現在もフッサールの著作を読むことができるのです。
まとめ
「人類の公僕」——学問全般のことを哲学とする。学問をする人は自分の私的な目的だけでなく、社会や人類に貢献しようとしている。
「人類の真のあり方」——どのような社会や文化のあり方を目指すべきか?
それを目標とする時に、狭い意味での哲学、つまり現象学のような学問によって共有できる理念をつくり、目標に向かって進むことが必要になるのです。
最後に、「本質観取」はそれぞれの思いをたずね合うようなところがある。
「ここは本当に人として共有できるよね」「リスペクトできるよね」といった気持ちを持ってほしい、ということでした。

番組内で実演された哲学対話も、ぜひ皆さんで実践してみてください。