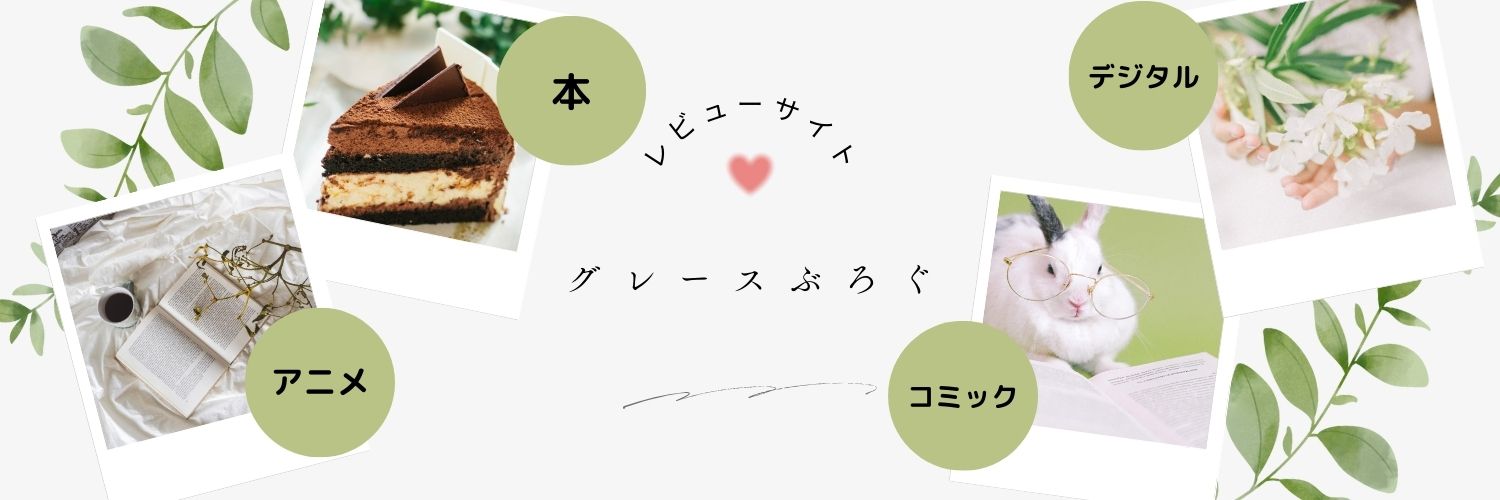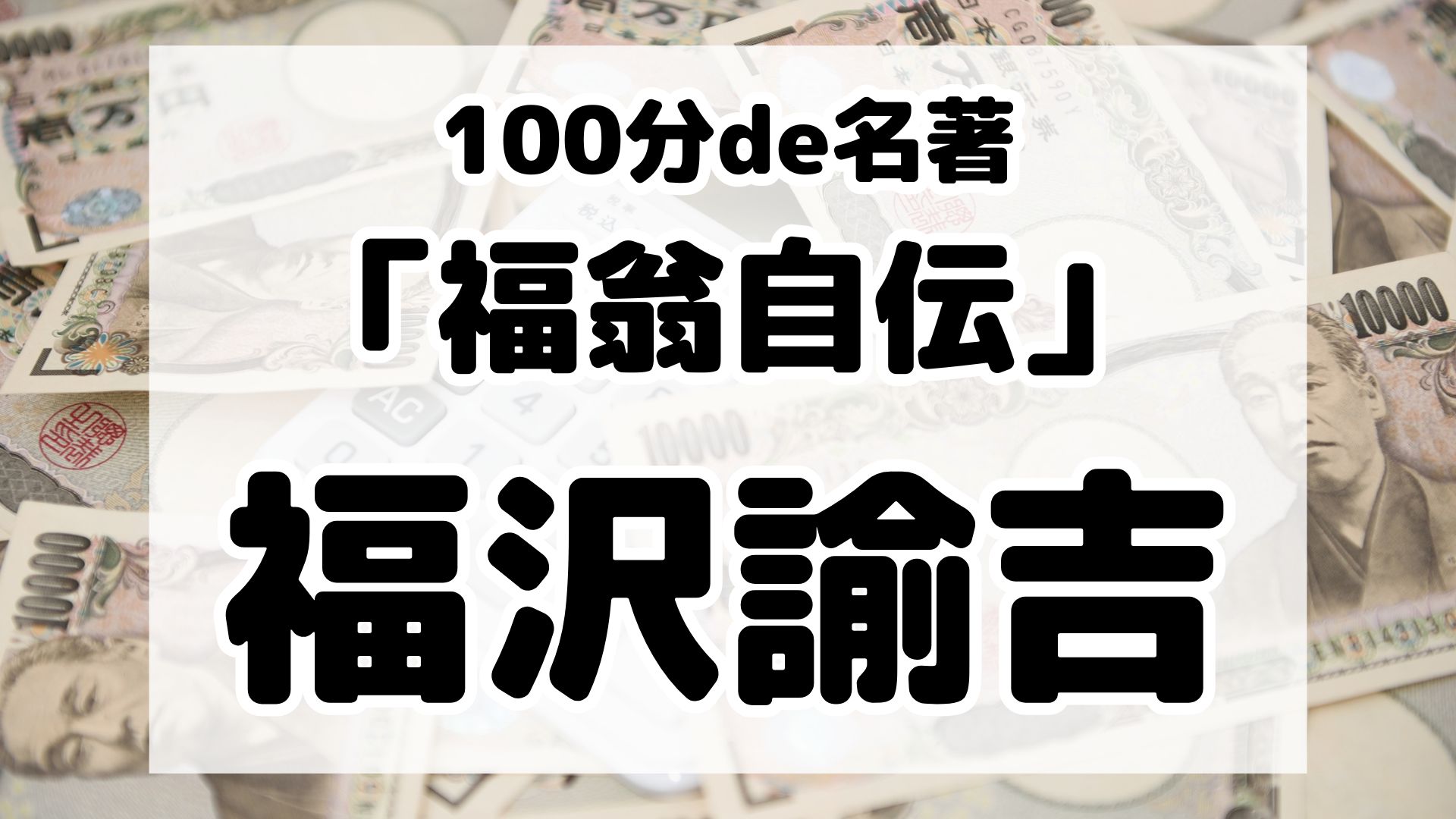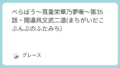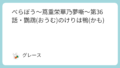福沢諭吉と言えば、1万円札の肖像だった人。
有名な著書と言えば「天は人の上に人を作らず」の「学問のすゝめ」をイメージする人が多いと思います。
今回は「福翁自伝」です。インタビューによる口述をまとめたモノです。
私も初めての著書です。
一緒に読み解いていきましょう。
第1回 カラリと晴れた独立精神
福沢諭吉は大分県の中津藩の下級武士の家に生まれます。
5人兄弟の末っ子です。
また、この中津藩の藩邸が大阪にあったので、福沢諭吉自身は大阪生まれということになります。

福沢諭吉は大阪生まれ
この誕生した地域も注目点ですね。
大阪の藩邸があった付近はまさに適塾があったところです。
適塾と言えば緒方洪庵。
あの日本の医師の草分け的な存在で、天然痘の治療に貢献した人です。
その適塾も近くにあり、何と福沢諭吉自身も緒方洪庵の門下であったというから、その学識の高さは素晴らしいものだったのでしょうね。
第1回ではその福沢諭吉の優秀な部分ではなくて、飄々とした性格が語られます。
「カラリとした精神」というのは指南役の斎藤先生の言葉ですが、こういう面白みのある人だとは私は初めて知りました。
面白いのはとことん合理主義であったことです。
宗教も権威も彼には通用しません。
何と罰当たりな話ですが、お稲荷様のご神体を石にすり替えてしまうのです。
それを知らずにお参りする人たちを見て面白がるのです。
その結果、別にだからと言って何か罰が当たるわけでも人が困るわけでもないといった感じでしょうか?
「宗教なんて意味がないね」と言いたげな感じです。
まあ、これを罰当たりと言ってしまえば、宗教的な話に戻ってしまいますが、福沢諭吉は今で言うデバンカーみたいなところもあったのだと思います。
これで、神仏に対してわざわざ砂をかけるようなことをしたというよりは、合理主義であったという方が重要なのです。
何もバカにしたり卑下したりするということではなかったのです。

福沢諭吉はデバンカーだった!
議論は論破しない
適塾や今で言う学生たちが集まるサロンでは当然、議論も起こります。
ヒートアップすることもあります。
でも、福沢諭吉は論破などせずに華麗にスルーするのです。
そこで相手をやり込めても意味がないことを分かっているからです。
現代の論破病にも通じますね。
相手を言い負かしたところで無用な敵を作るだけで、不毛な罵り合いになるだけですからね。
「門閥制度は親の敵で御座る」
門閥制度とは身分の上下があるというくらいに考えていればいいと思います。
ここでどうして「門閥制度が親の敵」なのかと言うと、身分の上下があったからこそ、貧しい武士の家の子供たちは家が継げないと僧侶になるしかなかったからです。
僧侶になるというのは現世を離れることであったり、貧しい生活を強いられるということであったのです。
そうすれば、子供を僧侶にするというのは親にとって苦渋の決断であったことが想像できます。

ですから、福沢諭吉はどんなに頑張っても報われない「門閥制度」が嫌いだったのでしょうね。
カラリとした精神に戻りたいと思います。
この精神を受け継ぐべきだというのです。
今のSNSや炎上、自分と意見が違ったら徹底的にたたくという風潮は私自身も愉快なものではありません。
自分自身がすこぶる迷惑をかけられているのならいざ知らず、全く利益も不利益も関係ない人をたたく必要はあるでしょうか?
ここは私たちも福沢諭吉の「からりとした精神」に倣うところは多いかもしれません。
第2回 自分を高める勉強法とは

第2回には適塾の緒方洪庵先生とのエピソードが紹介されます。
福沢諭吉が緒方洪庵の直弟子だったなんてすごいですね。
この師弟関係も親子のような関係だったのですが、とことんフェアだったのです、
第2回は適塾の話です
適塾とは?
日本で初めてワクチンを作った緒方洪庵が設立した塾。
全国から医師を志す優秀な人たちが集まり、寝る間も惜しんで勉強に励みました。
成績は絶対!身分よりも実力主義
塾内の序列は武士か町人か年齢かに関係なく、ひたすら成績順。
純粋に「勉強できるかどうか」だけが評価基準でした。
諭吉と緒方洪庵の関係
諭吉は非常に優秀だったため、緒方洪庵からも特別に大切にされました。
腸チフスにかかったときには、冷静さを欠いた緒方洪庵が他の医師に治療を頼んだほどです。
フェアな精神と学費の工夫
諭吉が金策に困ったとき、緒方洪庵は翻訳の仕事を与えて支援。
学費免除という依怙贔屓はせず、フェアな対応を貫きました。

名医・緒方洪庵は福沢諭吉を息子のように大事に思っていたので
彼が腸チフスの時に冷静に判断できないほどでしたが、
決して特別扱いするわけではなかったというのが好感度ポイントです。
勉強法は「とにかくリピート」
「読む」「復習する」「話し合う」——徹底的な反復学習。
ノートを必死に書き写すことで記憶に刻み込みました。
英語を第二外国語として習得
オランダ語に精通していた諭吉ですが、実際の海外で英語が通じず挫折。
しかし諭吉は落ち込むことなく猛勉強し、英語まで習得してしまいました。
斎藤先生のエピソード
「33歳で無職だった」という自身の体験を披露。
それでも「自分ほど勉強した人間はいない」という矜持が次の一歩につながったと語ります。
適塾でのユーモアあふれるいたずら
遊女からのラブレターを偽装して仲間をからかう一幕も。
騙されたのは、なんとマンガの神様・手塚治虫のご先祖様!
そのエピソードは手塚治虫の『陽だまりの樹』でも描かれています。

手塚治虫のご先祖様も適塾で学んでいた!
第3回 人生の困難を切り拓く
咸臨丸に乗り込む!
咸臨丸にも乗り込んだという福沢諭吉。
勝海舟が有名ですが、この調査団に福沢諭吉もいたのです。
実はこの咸臨丸。
日本で造られた日本の船なわけなのですが、黒船来航の年から7年で造られた船です。
こう聞くと皆さんどう思われますか?
いくら何でも本当に海外に行って帰ってこられるんだろうか?
そう思いませんか?
ほとんどの人がそう言うわけです。

いくら外国に興味があって行きたいと思っても、生きて帰ってこられるかどうかわからない咸臨丸に進んで乗りたい人は、そんなにいなかったのかもしれません。
最終的に、酔狂な勝海舟と同じくらいの酔狂人だったのかなと思います。
見事な交渉術
咸臨丸に乗り込むための交渉術も面白いものです。
とにかく外国に行ってみたい福沢諭吉。
でも、自分は身分的にそういうポジションにいません。
諭吉は自分でコネクションを作るわけです。
咸臨丸の艦長になった木村摂津守に直談判するため、その親戚に自分の知人である蘭方医の桂川がいることを知ります。
その桂川に紹介状を書いてもらって、木村摂津守に会いに行くのです。
医者なら諭吉も知り合いが多くいたので、可能だったことでしょうね。
それにしても、この情報収集力も素晴らしいことながら、行動力も素晴らしいですね。

面白いのは、艦長の木村摂津守にしても「渡りに船」だったということです。
前述したように、海外に行くなんて普通は考えられない時代です。
おまけに咸臨丸は黒船来航の7年後に造られたばかりの船。
生きて帰ってこられる保証はない。
こうなると、わざわざ行きたいという青年が現れ、おまけにその青年は勉学に秀でていて、独学で英語まで習得しているわけです。
木村摂津守にしても、超ラッキーだったのでは?ということなのです。
生きて帰れるかどうか分からない咸臨丸
医師であり英語も出来る諭吉がやってきたのは木村摂津守もWin-winだった!
レディファーストに驚き
実際にアメリカに行くと、女性と男性の地位が日本とは違うことに驚愕します。
いわゆるレディファーストなわけですが、これを「女尊男卑」と言ってしまうところにも、諭吉のセンスが光ります。
とはいえ、この後、記念写真には女性と一緒に収まっているのも、ちゃっかりしているなあと感じました。
諭吉が驚いたこと
・レディファースト
・グラスの中の氷
・馬車
・カーペット

今だったらそんなに驚くことではないかもしれませんが、こういったことがフレッシュな感覚だったのです。
そして素直に驚く諭吉。
うがった気持ちなどはなく、あっさり受け入れてしまう姿勢が、多くの知識につながっているのだなあと思います。
第4回 事業の達人に学べ
緒方洪庵へのリスペクトから生まれた慶應義塾
緒方洪庵の「適塾」にリスペクトして自分の学校を「慶応義塾」とした福沢諭吉。
時間割を決めて担当教員も決めるという、現代にも踏襲されている方法を始めます。
日本初の授業料制度を開始。
熨斗や水引などの「お礼」も必要なし。
塾生から受け取った金銭は教員の間で分配されていきます。
非常に合理的で、身分の差なく教育を受けることができます。

…とはいえ、教育を受けるのに「お金」は必要だったわけです。
経営という時点で、学校教育で最初に成功したと言えるわけです。
福沢諭吉が生きている間にも、経営がうまくいっている時だけではないわけです。
西南戦争の時は教え子も教師も激減し、つぶれても仕方ない状況も経験しています。
この時でも飄々として乗り切ってしまいます。
「メンタル・タフネス」というのは斎藤先生の評価ですが、本当にその通りです。
千両分の紙を蔵いっぱいにする諭吉
福沢諭吉の経営のうまさは、千両分の紙を蔵いっぱいにしたということです。
何のことかと思う人も多いかと思います。
千両分の紙というのは大変な財産です。
それが蔵いっぱいあるわけですから、これを見た人たちはどう思うでしょうか。
こんなにあるなら、どんどん仕事がある人に違いないとか、金払いが良いに違いないと思われるわけです。
そう思われたなら諭吉の勝利です。
「ここだけの話」や「お得な情報」がどんどん入ってくるわけです。
人心掌握術にも非常に長けていたわけですよね。
そこで得た情報で、どんどん自分も豊かになっていくわけです。
経営者としての成功の秘訣ですね。
自然保全活動へ
そして最終的に、その私財をなげうって故郷の自然を守るのです。
素晴らしい渓谷が売りに出されていると知った諭吉。
心無い人に購入されて美しい景観が損なわれてしまうよりは良いと、自分で購入したのです。
さらに、自分の名前は伏せて購入したというのが格好いいですね。
今で言うナショナル・トラスト運動です。

学術的に天才でありながら、飄々とした人物であった福沢諭吉。
また、教育の経営者としても成功し、そのお金を自然保全のために使ったという、とことん前衛的な人物でした。
「学問のすゝめ」しか知らなかった私でしたが、多面的な天才であることを知ることができました。