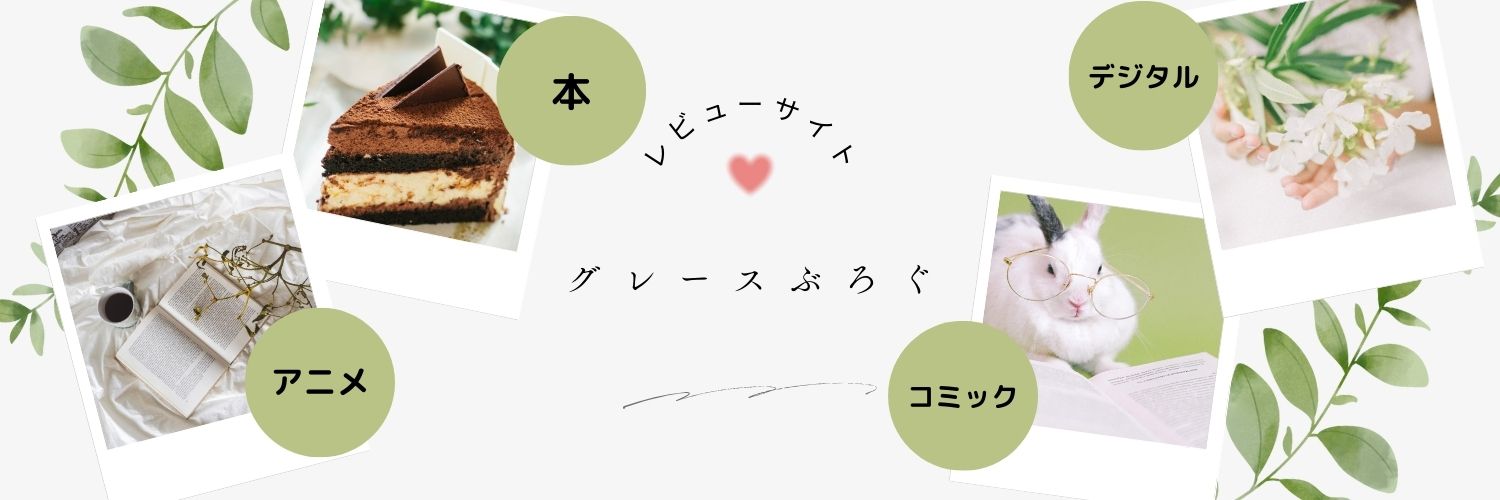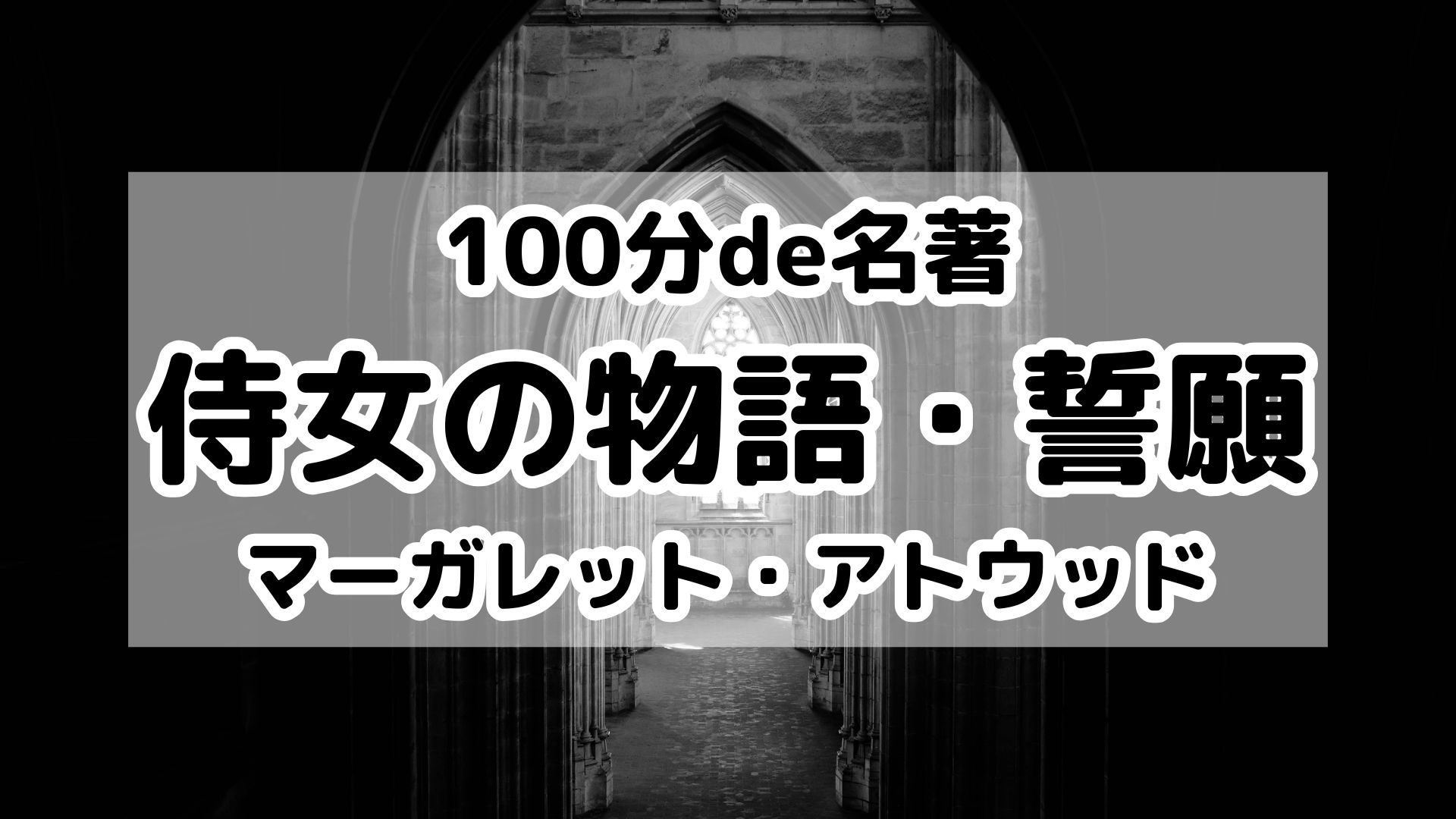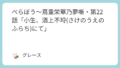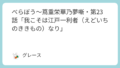マーガレット・アトウッドと聞いて思い浮かぶのは、「ノーベル文学賞候補の常連」ということです。
毎年、村上春樹とともにノーベル賞の時期になると名前が挙がる方ですね。
絶望的なディストピア小説の達人という印象を私は持っています。
第1回 すぐそこにあるディストピア
【初回放送】2025年6月2日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
舞台であるギレアデ共和国は、近未来のアメリカにキリスト教原理主義者達が創設した宗教国家。内戦状態にあり国民は制服着用を義務づけられ常に監視下に。逆らえば即座に処刑される。環境汚染、遺伝子操作等の影響で出生率が低下し、数少ない健康な女性は子供を産むためだけの道具とされ、支配者層である司令官たちに「侍女」として仕える。侍女の一人オブフレッドは体制に疑問を持ちながらも支配階層との儀式的な性行為を強制され人間の尊厳を踏みにじられ続ける。体制に従わない人々は次々に処刑されていくのだった。第一回は、「侍女の物語」「誓願」双方で描かれる過酷な全体主義国家の圧政のしくみやそれに苦しむオブフレッドの姿を通して、現実社会とも相通じる抑圧やジェンダー差別、強権的な政治手法の問題を浮き彫りにしていく。
アトウッド作品とディストピア小説の世界
アトウッドの作品自体は、とても暗い話になります。
いわゆるディストピア小説ということになりますが、特に第1回ではなかなか面白い見解がありました。
ディストピアとは何か?
ディストピアとは、「理想郷(ユートピア)」の反対です。
暗黒世界や支配的な社会で人が生きていくという、絶望的な話が多いです。
ディストピア小説は、読み手の精神力もけっこう必要というイメージがあります。
空想では済まされないアトウッドの現実感
アトウッドの作品は重いテーマを扱っていますが、それが「空想」とは言っていられないほど現実とリンクしています。
話題になる作品は多いのですが、今回は『侍女の物語』と『誓願』について考えていくことになります。
この二つの小説は違うタイトルですが、実際は続きのお話です。
つまり、『侍女の物語』と『侍女の物語2』というイメージで考えてもらうとよいでしょう。
名前すら奪われた主人公「オブフレッド」
『侍女の物語』では、主人公の女性の名前がすでに隷属的です。
「フレッド」という男性の所有物という意味で、「オブフレッド(Of-Fred)」と呼ばれます。
彼女は「オブフレッド」となる前は、夫と子供とともに普通の主婦として暮らしていました。
そんな暮らしを、「まだ子供が産める年齢だから」という理由で家族から引き離され、
司令官となった男性の子供を産むために侍女として仕えることになるのです。
何のことか訳が分かりません。
主人公の女性にとっては、もっと訳が分かりません。
離れて暮らす家族の安否すらわからないまま、絶望の中で生きていくのです。
さらに言えば、彼女の本名は原作小説では明かされていません。
※実は映像化にあたってわかりやすくするために、映画版では「ケイト」、ドラマ版では「ジューン」と設定されていますが、原作では全編を通して本名は奪われたままです。ここが非常に恐ろしい点です。
ディストピアは「意図して作られた」ものではない
今回の指南役である鴻巣さんは、アトウッドに実際に会って話をしたことがあるそうです。
その中で、「ディストピアにしようとしてディストピアになったわけではない」という言葉がありました。
『侍女の物語』のなかで、司令官や為政者たちも最初は「良い社会」、むしろ「理想郷(ユートピア)」を作ろうとして始まったというのです。
理想が恐怖に変わるとき
これは、かつての寓話や神話などでも繰り返されてきた話かもしれません。
今、現代によみがえったこの物語の中で、私たちの社会も同じことを繰り返しているのではないでしょうか。
完璧な社会を目指すあまり、少しでも間違いを犯した人を徹底的に糾弾し、
恐怖政治へとつながっていく――そんなプロセスが描かれているように思いました。

専制社会の「悪」の為政者たちも「悪」だと思っていた私にとっても
為政者たちが「善」から始まったということに新たに恐怖を感じずにはいられません。
第2回 性搾取の管理社会
【初回放送】2025年6月9日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
支配体制を支える「小母」、権力者である司令官に嫁ぐ「妻」、家事やケア労働の一切を担う「マーサ」、子供を産むための道具「侍女」…女性は4つの階級に分類。分断支配され、徹底して「性」を搾取されていく。支配者達は「女性たちを余計な競争や困り事から解放してやったのだ」と嘯くがそれは巧妙な詐術だ。物語を読み解いていくと「~からの自由」「~への自由」という人間にとって本質的な自由概念の区分に行き当たる。この国家には部分的に「~からの自由」という消極的な自由はあるかもしれないが、どんな存在にもなりうるという「~への自由」、積極的な自由は女性たちから決定的に奪われているのだ。第二回は、女性達を分断支配する巧妙な仕組みに焦点を当て、どのように性搾取の管理社会が成り立っているかを明らかにする。
『侍女の物語』第2回の衝撃的なオープニング
侍女の物語は、女性の権利を踏みにじり、子どもを産む機械として描かれていく非常に不愉快な話ですが、第2回はオープニングから、まるでこの女性が種付けされるかのようなイラストで始まります。
この話が『100分de名著』で語られたのは、2023年の新春スペシャルでした。
その時の画像が再利用されています。
最初に観た時にもかなりの衝撃を受けましたが、まさかメインの番組でもこれを踏襲するとは思いませんでした。
「司令官の妻」が実権を握る構造
出産経験のある女性=出産可能な女性を、現実的にはさらってきて司令官にあてがうわけです。
もちろん、そこに愛情などは一切なく、司令官の妻に捕まえられ、監視下で行為が行われます。
ここでは人権など存在せず、一番の実権を握っているのは司令官ではなく、「司令官の妻」だというのです。
自分の夫の子どもを産む女性を管理しているのが、この司令官の妻だということなのですね。
私は、ディストピアの世界では統治者が実権を握っていると解釈していたので、「司令官の妻」がそれに当たるというのは新たな視点でした。
翻訳においても、ニュアンスの違いがありました。
子どもが産めない女性の末路
侍女にされた女性も、3人の司令官との間に子どもができない場合は、コロニーに送られます。
そこは放射能に汚染された場所で、「子どもが産めない女性は廃棄される」とでも言うような、恐ろしい状況です。
それを逃れるためには、司令官の相手をする娼婦になるという道しかなく、どこまでも不愉快な話です。
女性の人権はまったく存在しません。
この空想上の話であるディストピア小説が、現代の現実ともリンクしていて、女性の価値が「子どもを産むかどうか」で量られるのです。
男性にも自由はない
ただ、よく考えると、男性側にも自由な権利はありません。
「種馬」程度の扱いなのが現状ですからね。
第3回 言葉を奪われた女たち
【初回放送】2025年6月16日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
「侍女の物語」の結末から15年。依然としてギリアデ共和国は安泰を保っていた。司令官の妻になるべく「読み書き能力」を奪われ従順に育てられるアグネスは幾つかの事件から体制に疑問をもち、自ら「小母」になりたいと志願、教育を受けることに。リディア小母はアグネスに特別な関心を払いながら「読み書き」を教え、国外から新しい国民としてスカウトしてきたデイジーの教育係に任命する。言葉の力を得たアグネスは体制への疑問をますます膨らませるのだった。第三回は、三人の登場人物の視点によって徐々に明らかになっていくギリアデ共和国の全体像を通して、言葉や知を権力によって奪われる恐ろしさに迫る。
『誓願』は女性たちの反撃の物語
「侍女物語2」と言って良い『誓願』は、女性たちが立ち上がる物語です。
『誓願』の元々のタイトルは『ザ・テストメンツ』です。
「テストメンツ」というのは「聖書」を想起させる言葉だと言われています。
旧約聖書が「オールド・テストメント」
新約聖書が「ニュー・テストメント」
これを「聖書」と訳さずに『誓願』と訳すのも、翻訳者のセンスが光るところです。
『誓願』と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか?
私は「神様に誓いを立てて、その道に入る儀式のこと」だと考えています。
では、この誓願は何に向かって誓っているのかというと、
「悪政を倒す」ことを誓っている、ということになりそうですね!
リディア小母という複雑な存在
『誓願』は、3人の女性による語りで構成されています。
第3回のこの回では、なんとリディア小母が語り部です。
侍女よりも、司令官の妻よりも上の立場の人です。
むしろ、侍女たちの権利を奪ってきた存在です。
そのリディア小母が、悪政の転覆計画を立てている首謀者の中心人物になっていきます。
『侍女の物語』の中では、彼女の思想によって苦しめられるのは「侍女たち」や「司令官の妻たち」です。
為政者たちと手を組み、女性たちの敵のような存在でした。
「悪政」を何かと正当化し、それをまた理路整然と女性たちに語っていた人物でもあります。
まさに、この「理路整然」というのがすごいところですね。
リディア小母は「読み書きすらできない女性たちの中では類を見ない、超インテリ」と言えるでしょう。
非常に高い教養を持った女性ということになります。
リディア小母はこの地位を得る前に拷問を受け、それを耐え抜いた数少ない一人として、やがて女性たちを支配する側に立ちます。
ですが、よく考えてみると、そんな経験をした彼女が、果たして悪政に従順で積極的な為政者になりえたのか、という疑問が湧いてきます。
リディア小母の過去が語られるのは、この『誓願』が初めてです。
こうなると、「彼女はリディア小母になる以前から、悪政を倒すために拷問を生き延びたのではないか」とさえ思えてきます。
読み書きの力が、世界を変える
女性でありながら、読み書きや高い教養を許される地位に上り詰めたうえで、彼女は悪政の転覆をもくろんでいたわけです。
高い地位に就いていなければならない、しかも教養も必要。
さらに言えば、「バレたら自分が殺される」のです。
これはまさに、長期的で自分の人生をかけた計画です。
その間には、多くの女性たちの恨みを買うことにもなります。
それらすべてを覚悟していたとは、本当にすごすぎる。
『侍女の物語』の世界で、女性たちは「おかしい」とは気づいています。
でも、それを打破する方法を知りません。
生き延びるためには、侍女であることを受け入れるか、死ぬしかないという状況だったのです。
そんな中で、文字を読める人たちが自分の考えや置かれている状況を言語化していくことで、女性たちの反撃が始まるのです。
これは私自身もすごく共感できるのですが、こうやってブログで自分の考えを整理していくことで、作品への理解がより深まったと感じています。
女性たちが「読み書きを覚える」「本を読み始める」ことで、正当な権利を主張できるようになる。
ワクワクしますね。
「1冊の本」「1本のペン」——この重みを感じる回でした。
第4回 闘う女たち
第4回 闘う女たち
【初回放送】2025年6月23日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
支配階層に仕えているかに見えたリディア小母は、裏で謀略を画策していた。スキャンダルを外の世界に公開し国家を崩壊に導こうというのだ。そしてデイジーは実は反体制グループによって派遣された情報の運び屋だった。数奇な運命を経て巡り合ったこの2人とアグネスは連帯。アグネスとデイジーは協力してギリアデを脱出、独裁国家を葬るべく極秘情報を国外へ持ち出すのだった。第四回は、徐々に洗脳を解かれていくアグネス、外の視点から体制の矛盾を明らかにするデイジー、体制の弱点を突くべく協力体制を築いていくリディアの姿を通して、虐げられている人々が過酷な状況に抵抗していくために何が必要かを考える。
物語の鍵となる「カナダ育ち」の少女デイジー
カナダ育ちの高校生デイジーの話になります。
この「カナダ育ち」というのが物語の伏線ですね。
「カナダ生まれ」とはならないわけです。
デイジー自身は幸せな子供時代を送っています。
それこそ、愛されて育つわけです。
そして、彼女自身は「文字を読める教育を受けている」ということなんですね。
デイジーの衝撃の秘密
彼女には秘密があります。
簡潔に言うと…。
- 両親は実の親じゃなかった!
- 自分は侍女が産んだ子供だった!
- 伝説の子供「ニコール」だった?
伝説の子供「ニコール」とは?
デイジーは自分自身が伝説の子供「ニコール」だったか否か?
この話には意外と言及されていないことも多い印象を受けます。
「侍女の物語」の「オブフレッド」と「ニック」の間に出来た子供で、ギレアデから脱出した後に生まれたのではと思われます。
(本当の所はリディア小母しか知らない!!!)
女性たちの「その後」が描かれない恐怖
侍女たちだけでなく、女性たちのその後が分からないのが本当のところであるというのがこの本の恐ろしさであると思います。
リディア小母の選書と引用された文学作品
誓願の中で引用される他の物語
リディア小母は超インテリです。
その彼女が自分の特選の本として選んでいる本がまた癖のあるモノばかりです。
- ジェイン・エア
- アンナ・カレーニナ
- テス
- 失楽園
有名どころの前時代的な女性達の話が並びます。
これらを聞いて、前時代的と思うのは、この話では少し滑稽です。
だって、この「誓願」は未来の話なんですから。
古典文学の女性たちは本当に「幸せ」だったのか?
ただ、これらの引用された他の物語は、どの女性も幸せな人生とは言えなかったと思います。
意外に「めでたし、めでたし???」で終わっているという解釈もあるようですが…。
私はそれはそれで驚いたことがあるのですが、みなさんはどう思われますか?
*ジェイン・エアは「豪邸に引きこもり」、アンナは「自殺」、テスは「処刑」だったように思います。
(記憶違いならすみません)
ノーベル賞作家アリス・マンローとアトウッド
さらにこのリディア小母のコレクションの中にはアリス・マンローの作品もあります。
アリス・マンローはカナダの作家でノーベル文学賞を取った人物です。
彼女がノーベル賞を取った時に私はアトウッドじゃないのかと思いました。
アリス・マンローとアトウッドは同世代の人物です。
アリス・マンローを知ったのはこのノーベル賞の時が初めてでした。
受賞当時で彼女の翻訳本は村上春樹氏による短編小説の1編くらいしかなく、それもまた話題になった作家です。
アリス・マンローとマーガレット・アトウッドが親友であったことも明かされました。
私は彼女たちはライバル関係であったのかと思っていたのでこれは嬉しい裏話でした!
文学における「男性目線」と女性像
被害者が男性なら女性がそそのかした事になる?
また、面白い視点もありました。
小悪魔的な、もしくはコケティッシュ(性的魅力がある女性)にそそのかされて男性が落ちていく場合、男性は「被害者」として扱われるというのです。
これは文学史上でもそうですね。
テキストでも「ロリータ」や「ファム・ファタール」などが紹介されましたが、これは大いに納得の解釈です。
やはり、文学や演劇の世界であっても「男性目線」で描かれるということも、かつてからあったということなのです。
これは私にとっては新しい視点でした。
女性が被害者なら男尊女卑で済まされる。
男性が被害者なら、女性が悪女ということになる。
(どのみち、女性が悪いという方向に持っていかれる)
結末には言及せず——最大のネタバレとは
これから読まれる方の楽しみを奪ってしまってはいけないので結末についての感想は控えておきますが、この本では解決しないこともあるということが私からの最大のネタバレになります。
多分、多くの人が明らかにしたいであろう「侍女物語」の主人公のオブフレッドの行く末は「分からない」というのが本当のところです。

つまり、侍女風情の行く末など公式には分からない。
これがこの本の真髄の恐ろしさなのだと思います。
図書館からの蜂起!
さあ、これらの果てしない闘いに挑んでいったのは「女性たちが知識を持つ」ということから、始まったのです。
ほとんどの女性の行く末は誰も分からない。
キチンとしたことはまず分からない。
これは、女性が「読み書き」が出来ないために記録をする事が出来ないという背景もありました。
そんな中で、非公式に「女性たちが学べる場」を作り、女性たちが蜂起するきっかけを作ったのはリディア小母だったわけです。
このリディア小母は「侍女の物語」の中では勧善懲悪の悪と言って良い存在です。
女性達にとっては絶対悪なくらいの悪です。
でも、そんなリディア小母は何千、何万という女性たちを犠牲にして多くの恨みを買ったうえで、バレたら自分が殺される事も飲み込んで何十年にも渡る壮大な計画を立てたのです。
一番すごいのは書ききったアトウッド
「侍女の物語」と「誓願」は非常に長い話です。
本を手に取った事がある人なら「重い」という感想を持った人も多いと思います。
この重さは本のテーマの重さでもあるなと私は感じます。
この重厚な長い話のほとんどが絶望的で閉鎖的な話なのです。
特に「侍女の物語」は救いらしい救いがありません。
そして、続編となる「誓願」の中でも女性たちは絶望の中で、ただ「知識を持つ」という1点で少しずつ体制を変えていくのです。
ここで、女性たちの蜂起であると私は考えていますが、一方で男性も幸せではないということを強く感じます。
つまりは、こういう全体主義というか専制主義というか、全くの自由がない世界では幸せな人が一人もいないということに尽きるのではと思います。
何がすごいかと言えば、これを書ききったアトウッド本人ということになりそうです。
多くのバッシングもあるでしょう。
評価が高い分の裏返しと言えばそうかもしれません。
ただ、これを物語にして、具現化できるのはやはりアトウッドを置いていなかったということです。
また、読者の読み解く力も必要なうえに精神力もかなり必要な作品でもあります。

これから読まれる方には、精神力を鍛えてから覚悟してお読みください。
(冗談でなく、本当に)
おまけ~アトウッド来日時のインタビュー
アトウッドは日本に来日した事があります。
これ、2010年の事でした。
私は前もって知ることはなかったのですが、NHKのブックレビューで一部が紹介された事がありました。
この「100分de名著」の中でも放送されるのでは…とワクワクしていたのですが、残念ながらありませんでした。
その当時の印象について、私が覚えている限りを書いておきます。
既にディストピア小説をたくさん書いていて、暗いテーマが多い作家だという印象があったので気難しい人なんじゃないかと思っていましたが、ものすごく明るい美女という印象でした。
そして、日本人向けの講演やインタビューだったので「とてもゆっくり」話すとても優しい方でした。
その内容もウィットに富んだ感じで、楽しい話ばかりだったのでこれもとても驚いた記憶があります。
この内容は当時のBSブックレビューという番組内で放送されました。
本が大好きなことで有名な俳優の児玉清さんがMCをされていたので、ご記憶の方も多いと思います。
放送当時は録画して何度も観たのですが、私の手元からはいつしかその録画したものもなくなってしまいました。
また、いつかあのインタビューを観る事が出来たら良いなと思いつつ、再読したいと思います。

アトウッドの裏話がたくさん聞けて楽しい100分de名著でした。
また、皆さんの感想もお聞かせ願えたらと思います。