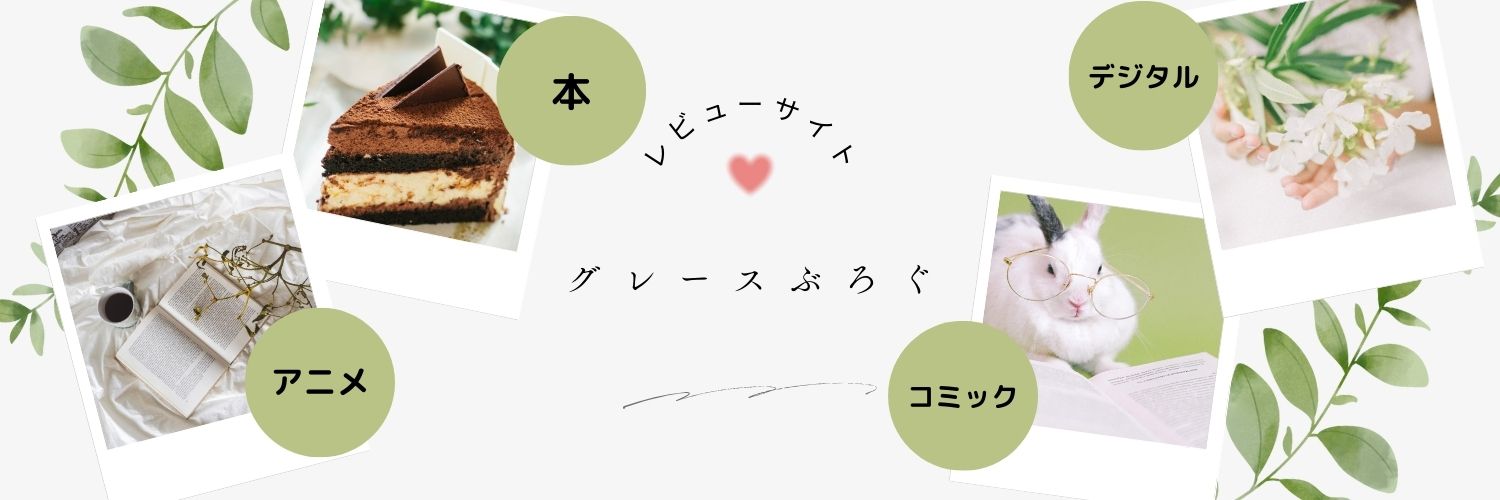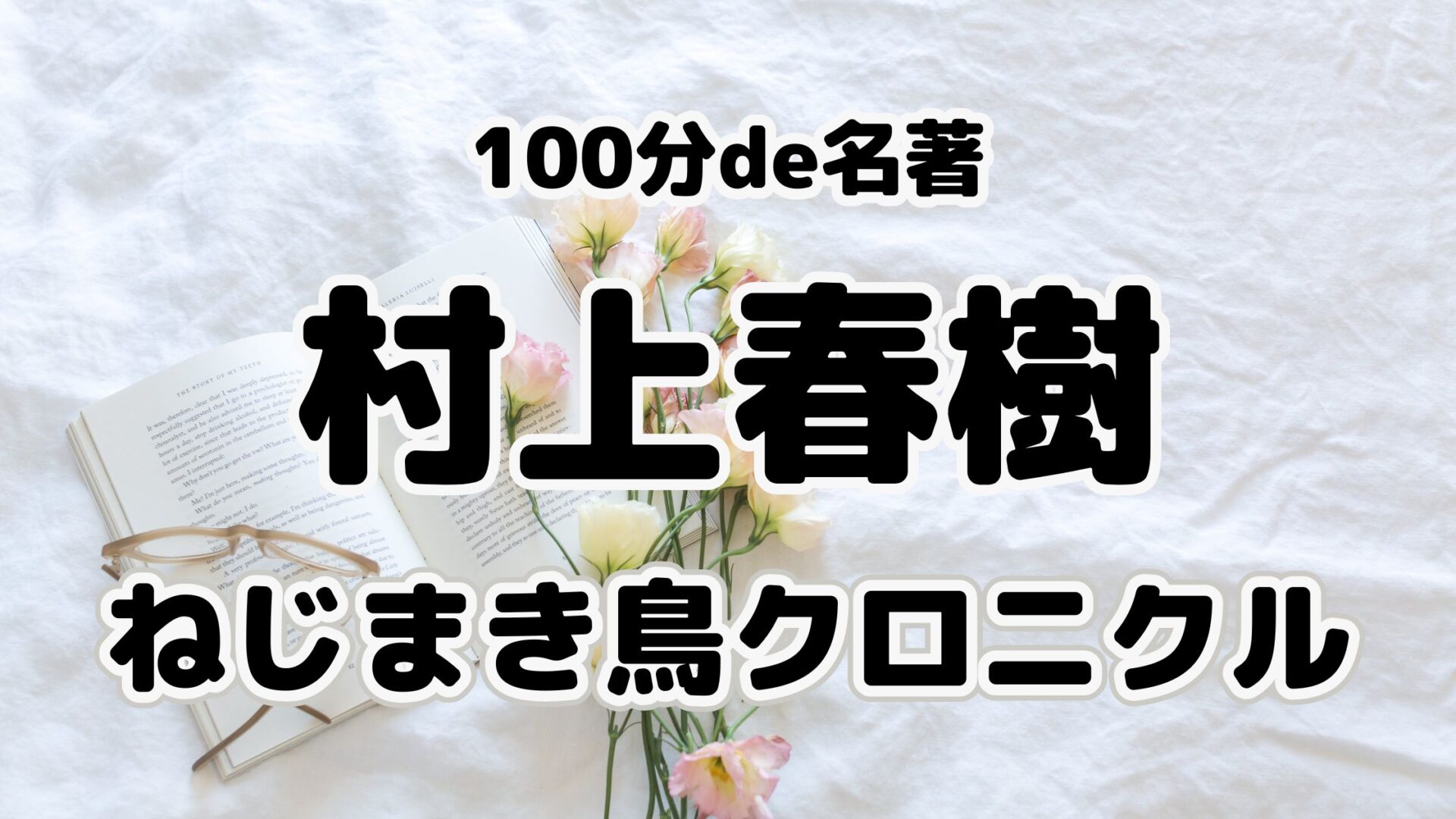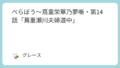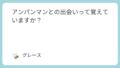世界でもっとも有名な作家の一人と言っていい村上春樹。
寡作ですが、出版のたびにニュースになるので読んだことがなくても知る人は多いはず。
私自身もこの作品は今回で初めて読む事になります。
全三巻、購入してきました!
一緒に読み解いていきましょう。
各回、目次からジャンプできます。
第1回 日常のすぐ隣にある闇
「僕」こと岡田トオルがクミコと結婚して6年後、大切にしてきた飼い猫が突然失踪する。クミコに頼まれて自宅の裏路地で猫を捜索するが気配すらない。この捜索をきっかけにトオルは次々に奇妙な人物たちと出会う。過去の事件にトラウマを持つ女子高生・笠原メイ、特殊能力を持つ加納マルタとその妹クレタ、国際紛争の地ノモンハンでの悲惨な体験を語る間宮中尉……どこにでもある日常を生きてきたトオルに突如として非日常的な時空が立ち現れるのだった。第一回は、作品の執筆背景にも触れながら、村上春樹が描き出す登場人物や舞台装置を通して、私たちの日常のすぐ隣にある深い闇の存在について深く考察する。
感想
この作品のベースになる事件として、「ノモンハン事件」というものがあります。
調べてみたところ、1939年の出来事です。
戦時下の事件なので、「とりあえず聞いたことがある」という程度の人も多いと思います。
(私もその一人です)
このときの捕虜の扱いについての描写があまりに酷いため、指南役の沼野先生は「創作」なのではないか推測しています。
(ただし、捕虜の扱いが正当でなかったのも事実です)
主軸となる物語は1980年代で、そこから40年ほど経っているということ。
男性が台所に立ってスパゲティを作るという表現が、「男のくせに稼いでいない」といった意図に結びついているとも言われています。
村上作品は、それぞれの登場人物の描写や時代背景が丁寧に書かれていると思います。
だからこそ長編になるわけですが……。
『ノルウェイの森』の話題にもなりました。
実は私自身、村上作品の「お初」は『ノルウェイの森』でした。
確かに気色の悪い小説で、途中何度も吐きそうになりながら読破しました。
(その初読以来、再読はしていません)
どんな思いで読んだかというと、「官能小説」と「純文学」はどう違うのか、真剣に考えさせられた作品でした。
そもそも読み進めたのも、親戚に強く「読むように」と手渡され、あの緑と赤の上下巻を一晩で読むという所業に及びました。
(今でも、あれは無茶ぶりだったと思います)

そんなことを思い出した第1回でした。
第2回 大切な存在の喪失
トオルが失業して3か月がたったある朝、クミコは雑誌編集の職場に出かけたきり、何の前触れもなく失踪した。トオルはやむなくクミコを探し始めるが手がかりは全くつかめない。近隣の空き家にある井戸の底での不思議な出来事など様々な事件を通じて、いかに自分がクミコのことを何一つ知らないかを思い知らされていく。そんな中、クミコから届いた手紙には「もう探さないでほしい」と書かれていた。一体、クミコに何があったのか。第2回は、かけがえないものを失ってはじめて得ることができた主人公の気づきを通して、私たちが大切な存在とどう向き合っていけばよいかについて問い直す。
井戸の描写に対する新たな理解
主人公のトオルが井戸の中に入るというのは、彼の妄想だと思っていたので、本当に井戸があって、その中に入り、底の方で一人考え込むという描写は、今回初めて知りました。
(私が勘違いしていただけなのですが……)
村上作品における「性的な闇」
村上作品の「性的な闇」の部分がクローズアップされた回だったと思います。
このほかにも、性的な描写が写実的すぎて気色悪いと感じるものは他にもあります。
官能小説と文学小説の境界線
第1回でも取り上げられた「ノルウェイの森」でもそうでしたが、あれほどの描写になると、「官能小説」と「文学小説」の境目とは何なのだろうか、と思います。
正直なところ、その明確な線引きはないのかもしれませんが、「ノルウェイの森」で吐くほど嫌な気分になった私としては、帯にでも「この小説にはかなり性的な表現があります」と書いておいてほしいと思うくらいです。
ねじまき鳥に描かれるタブー
この作品『ねじまき鳥』の中にも、性的なタブーに踏み込んでいます。
ですが、これは誰しもがぶち当たるテーマでもあるかもしれません。
ここまで直接的でないにしても……です。
不倫や堕胎をめぐるテーマ
性的なテーマは、不倫や堕胎にも及びます。
「自分は裏切られていたのでは?」「その子供は誰の子だったのか?」
そういったことで、トオルは自分では解決できず、また井戸の中で一人悩み込むわけです。
他作品との共通点
このテーマは、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』でも描かれていたなあと思います。
第3回 根源的な「悪」と対峙する
村上春樹“ねじまき鳥クロニクル” (3)根源的な「悪」と対峙する
初回放送日:2025年4月21日
井戸に潜ることを始めたトオルは、クミコ捜索を阻んでいるのが彼女の兄・綿谷ノボルであることに気づく。やがて綿谷から連絡が入り、自分の活動を邪魔しないことと引き換えに、パソコン通信でクミコと会話することを許される。だが彼女の心には深い闇が存在することが明らかに。トオルは、彼女の闇の源であり、根源的な悪ともいうべき綿谷との対峙を決意するのだった。第三回は「根源的な悪」とどう対峙(じ)したらよいかを考える
第3巻は2回に分けての放送に
最終巻の第3巻を『100分de名著』では第3回と第4回の二つに分けて考察していく回になりました。
もう、本文は読むしかなくて、時代背景や登場人物の説明になっていきました。
舞台は1980年代、トオルの葛藤
この作品は1980年代をモデルにした作品です。
主人公のトオルは相変わらず右往左往しています。
そんな中で猫の名前にも付けられた「ワタヤノボル」は、何と政界進出していきます。
東大を出て、イエール大に行き、経済学者になってテレビの人気コメンテーターになり、国会議員になるという——ステレオタイプというか王道の人生を歩んでいるわけですね。
これがトオルにとっては、妻の兄、すなわち義兄であるからこそ、悶々としてしまうわけです。
ですが、このワタヤノボルは絵に描いたようなクズでもあって、この辺が村上作品の面白いところだなと思います。
また、この“クズな部分”が「性犯罪」とか、そういうレベルなのです。
(詳しくは書きません。本書を読んでください)
スピリチュアルな親子、ナツメグとシナモン
この第3巻に出てくる印象的な人物として、「赤坂ナツメグ」「赤坂シナモン」という親子が登場します。
今で言うスピリチュアル系の親子です。
はっきり言って人を騙してお金を取っているわけですが、本文を読む限り、本人たちは本気でそういう能力があると信じています。
かつ、トオルを騙そうとしている感じがします。
「スピ系」という言葉がなかった時代です。
トリックは簡単で、ホットリーディングとかコールドリーディングと呼ばれる手法。
今思えば、それほど難しいことではなかったのかもしれません。
でも、そんなことに騙される方も、騙す方も、「スピリチュアル」があるという前提で話が進んでいく——
この構造そのものが、村上春樹の筆致のなせる業なのかもしれません。
そして、騙し方のトリックというのは、今も昔も根本的なところは変わらないということです。
騙されるトオルの心情と読者の没入感
ナツメグとシナモン親子に騙されるトオルも、そもそも邪な心があればこそ騙され、心酔していくわけなので——
この辺りも、読んでみて引きずり込まれる感覚を、皆さんにも味わってほしいと思います。
「パソコン通信」と時代のずれ
そして、「パソコン通信」という言葉も登場します。
これは、パソコンが出回り始めて最初に使われていた言葉です。
パソコンが一般に広まり始めたのは1990年代。
この作品の主な時代が1980年代なので、10年ほどズレている感覚があります。

こうやって時空をうまく超えているのも、村上作品だったなあと改めて思いました。
第4回 「閉じない小説」の謎
村上春樹“ねじまき鳥クロニクル” (4)「閉じない小説」の謎
初回放送日:2025年4月28日
悪の正体を突き止めるべく再び井戸に潜るトオル。彼は壁を抜けて異界へ侵入するが、そこでは既に綿谷ノボルが何者かにバットで殴られて重体に。窮地に陥り逃げ込んだホテルの一室には闇にとらわれた謎の女性がいた。彼女にバットを手渡されたトオルは襲い来るおぞましき者を打ちのめす。やがて現実世界に引き戻されたトオルは、現実に起こった衝撃の事実と対面するのだった。第四回は、「閉じない小説」の豊かな可能性に迫る。
井戸の中に入るというのが空想ではなく、現実に存在する井戸の中に入るということで、トオルのヘタレっぷりには現代にも通じるものがあるのかもしれません。
文化や風潮は時代と共に変わっていくのかもしれませんが、この小説が今も色あせないのは、人の根本的な悩みというものが変わらないからなのかもしれません。