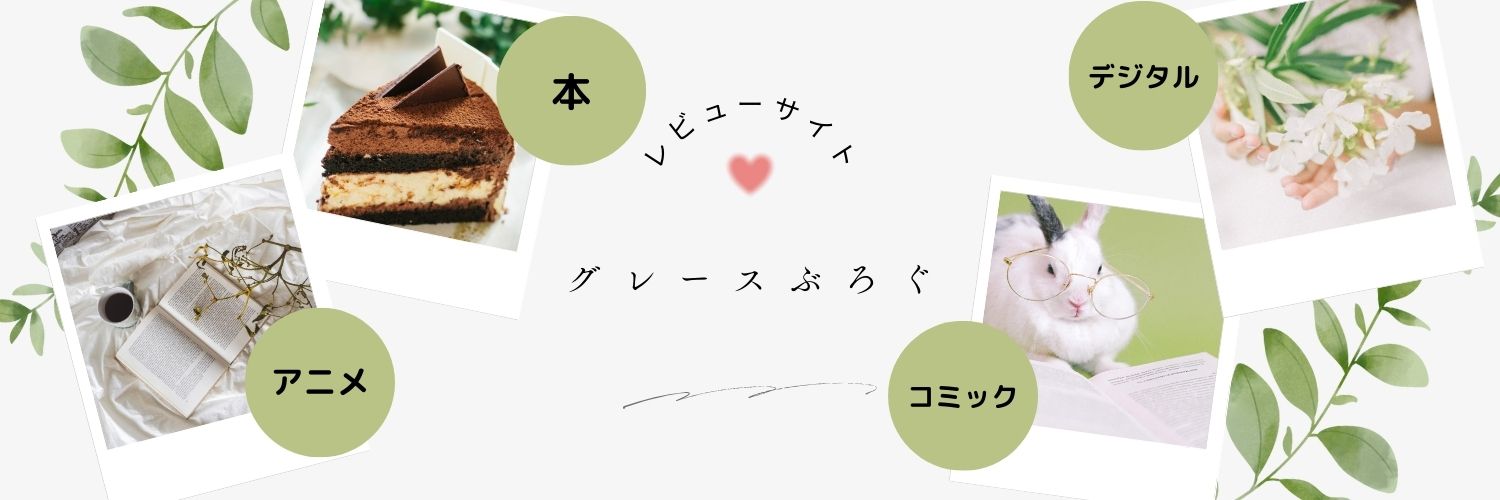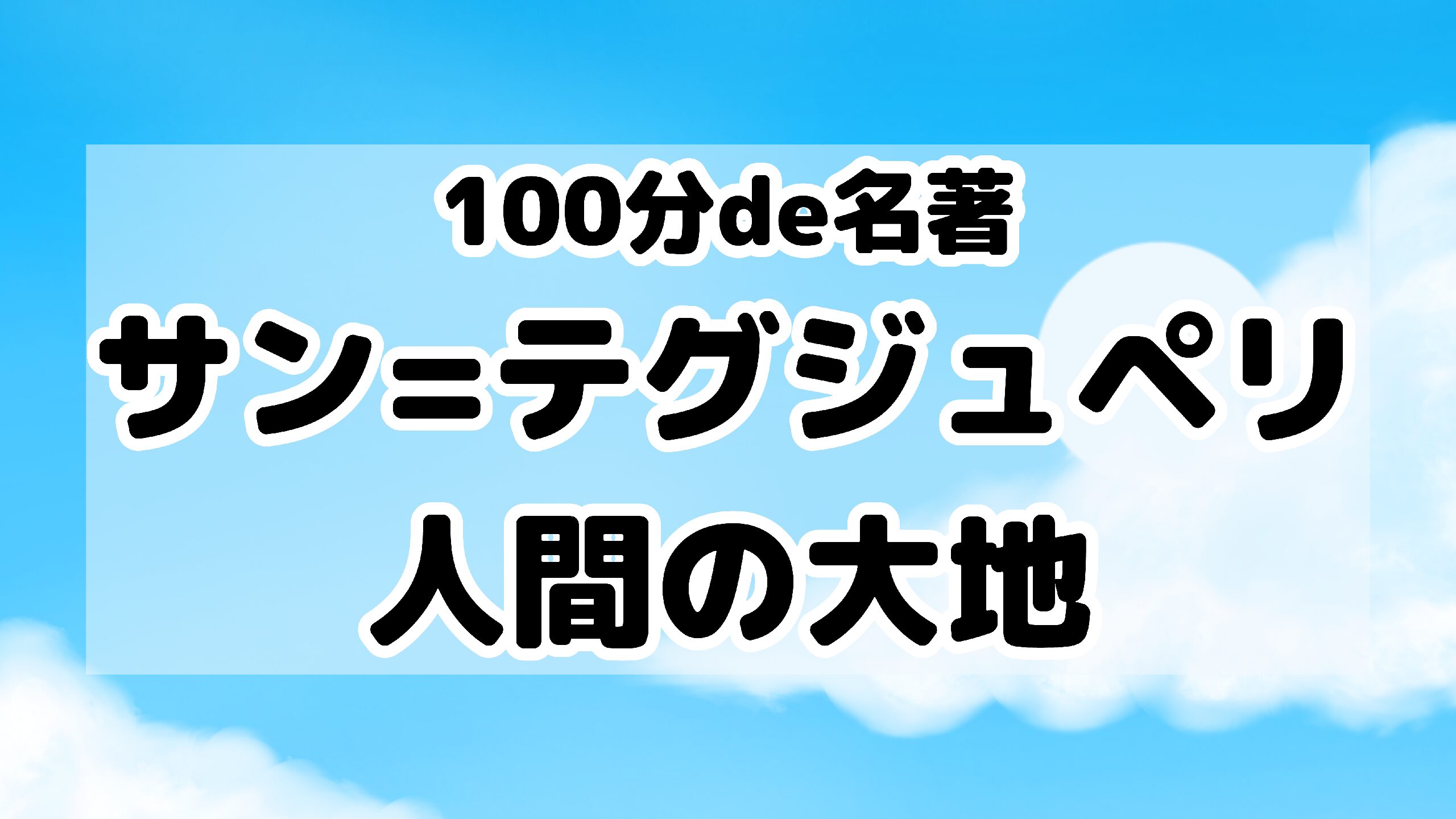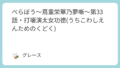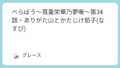星の王子さまで有名なサン=テグジュペリです
その骨子となったエッセイの「人間の大地」
私自身の思いが強すぎて感想メインになりました。
サン=テグジュペリについて
| サン=テグジュペリ 年表(主要事項) | |
| 1900年 | 6月29日、フランス・リヨンで誕生 |
| 1926年 | 作家デビュー(短編『南方郵便機』) |
| 1931年 | 長編小説『夜間飛行』刊行(フェミナ賞受賞) |
| 1939年 | 『人間の土地』刊行(アカデミー・フランセーズ大賞) |
| 1940年 | ドイツ軍のフランス侵攻により アメリカへ亡命 |
| 1943年 | ニューヨークで『星の王子さま』刊行(フランス語・英語版同時出版) |
| 1944年 | 7月31日、偵察飛行任務中にマルセイユ沖で消息不明(享年44) |
📘 代表作
『南方郵便機』(1926)
『夜間飛行』(1931)
『人間の土地』(1939)
『星の王子さま』(1943)
星の王子さまとは
サン=テグジュペリと言えば、「星の王子さま」ですね。
ファンタジーとして、小説として多くの人が知っている作品です。
「星の王子さま」は、自分の小さな星から旅立って、いろんな星に行くお話。
最後は星の王子さまが倒れてしまいます。
とても有名なこの作品ですが、実は意外に短いお話であることにも驚きます。
少し長めの絵本という感じがします。
100分de名著で取り上げられたのは「人間の大地」
NHKの「100分de名著」で取り上げられたのは、「星の王子さま」ではなく「人間の大地」という作品でした。
「人間の大地」とは小説でも童話でもなく、サン=テグジュペリが郵便飛行士としての体験を綴ったエッセイ集です。
中心となるのは、彼自身が墜落して遭難した時の話。
生き残ったからこそ、このエッセイを書くことができました。
「星の王子さま」の終盤には、遭難したパイロットと出会う場面があります。
これはサン=テグジュペリ自身がモデルであったということですね。
危険と隣り合わせの飛行士
この「人間の大地」。
飛行士は憧れの職業である一方で、とても危険でもありました。
当時は今よりも墜落や行方不明が多かったのです。
そして「人間の大地」の終盤では、第二次世界大戦の前触れのような出来事にも触れられています。
戦争の影
第二次世界大戦前のヨーロッパは、不穏な空気に包まれていました。
フランスに出稼ぎに行っていたポーランド人たちは解雇され、絶望の中、列車で自国へ帰ります。
その多くはユダヤ人であったのではないかと、指南役の野崎歓先生は推察しています。
サン=テグジュペリ自身もユダヤ人であったことから、アメリカに亡命を余儀なくされます。
そして世界的に名を知られていた彼は、アメリカで「星の王子さま」を出版しました。
英語とフランス語の同時出版によって、自国の人々にも思いを届けたのです。
再び空へ
アメリカに亡命した後、彼はフランスに戻り、戦闘機のパイロットとして再び空に挑みます。
どうしても傍観者のまま終わりたくなかったのでしょう。
しかし、彼は撃墜されて消息を絶ちます。
享年44歳。(遺体は見つかっていません)
今にしてみればとても若い年齢ですが、パイロットとしては決して若いとは言えませんでした。
戦争がもたらした悲劇
敵側にも彼のファンは多く、「人間の大地」を読んでパイロットになった人もいたといいます。
もし戦争がなければ、こんな悲劇もなかったのです。

敵対した人たちの中にサン=テグジュペリのファンもいたのです。
<各回の放送内容>
第1回 飛行機乗りの仲間たち
【放送時間】2025年8月4日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
【指南役】野崎歓…放送大学教授。フランス文学者。
【朗読】山口馬木也(俳優)
【語り】目黒泉
航空産業の黎明期、人類は、これまで体験したことがない視点や感情をもつに至った。まだエンジンなどの技術も不安定な時代、常に死の危険と隣り合わせだったプロフェッショナルの操縦士たちが頼れるのは、かすかな予兆を感じとる研ぎ澄まされた感覚と、互いに支えあう仲間たちの絆だけ。それを裏打ちするのは、「人間であること、それはまさしく責任をもつことだ」という言葉の象徴されるプロフェッショナルたちならではの倫理だった。第一回は、黎明期の航空産業で働くプロフェッショナルたちの行動のドキュメントから、「責任とは?」「友情とは?」「人間同士の絆とは?」といった普遍的なテーマを考えていく。
第2回 惑星視点で見る
【放送時間】2025年8月11日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
飛行という体験によってもたらされた、大地を「惑星」としてみる視点。サン=テグジュペリは、その視点から、人間の営みのかけがえのなさを鮮やかに描き出す。星空へ落下していくような、めまいと重力の体験をもたらす夜間飛行は、宇宙との交感ともいうべき壮大なスケールの体験だが、それと鮮烈なコントラストをなす、家々に灯る小さな灯火を彼は見逃さない。広大な荒れ野の中にわずかばかり広がる人間の生存圏、日常の中で毎日清潔なシーツを用意してくれる老女の営み……宇宙的スケールの体験は、むしろ人間のささやかな営みの大切さを照らしだしてくれるのだ。第二回は、惑星視点から世界を眺めることで浮かび上がる、人間の営みのかけがえのなさ、尊さに迫っていく。
第3回 砂漠に落っこちる
【放送時間】2025年8月18日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
砂漠のど真ん中にある、航路の中継基地「キャップ=ジュピー」の過酷な環境がサン=テグジュペリの思想を鍛えた。「サハラ、それが姿を現すのはわれわれの内側においてである」との言葉が示す通り、砂漠では、時間が明晰な身体感覚として立ち現れ、大きな変化につながるわずかな自然の予兆を鮮烈な感覚として受け取るようになる。極めつけは、機関士プレヴォとともにした苛烈な遭難体験だ。飢えと渇きがもたらす極限状況では、すべてをはぎ取られた「いのちのかたまり」ともいうべき人間の本質が浮かび上がっていく。第三回は、砂漠という過酷な環境が炙り出す、人間の本源的な姿を明らかにしていく。
第4回 人間よ、目覚めよ!
【放送時間】2025年8月25日(月) 午後10時25分~10時50分/Eテレ
軍靴の音が響き始める第二次世界大戦前夜、生と死のはざまにあった人々の姿も、サン=テグジュペリは活写する。出撃前にかすかな笑顔をみせるスペイン内戦に従軍した兵士の姿、三等列車で移送される粘土のように疲れ切った移民の群れ、その中で唯一輝く存在だった子ども。人間性を踏みにじる過酷な状況を「モーツァルトの虐殺」と呼ぶ彼は、どんなに目立たないことであっても、自分の役割を自覚することで人間は幸福になれると考え、「愛するとは互いに見つめあうことではない。一緒に同じ方向を見つめることだ」という言葉を刻み込む。「絆」、そして「精神の息吹きを通わせること」だけが、人間を再び創造することになるというのだ。第四回は、生と死のはざまにあって、なお、朽ちずに輝きわたる人間の尊厳や絆について考える。